松飾りいつから飾る?時期とルールについて徹底解説!正月準備を始めよう
年末が近づくと、「松飾り いつから飾ればいいのだろう?」と気になる時期ですね。正月 松飾りをはじめとするお正月飾りは、新年を迎えるための大切な準備の一つです。特に玄関 飾り 正月 いつから飾るかは、多くの人が悩むポイントではないでしょうか。
この記事では、そうした疑問にお答えするため、お正月飾りのルールを詳しく解説します。また、松飾りの簡単な作り方に触れつつ、新年の挨拶にふさわしい贈り物や、一年頑張った自分へのご褒美、家族で楽しむために役立つ情報もあわせてご紹介します。
- 松飾りを飾り始めるのに最適な日付
- お正月飾りを飾ってはいけない縁起の悪い日
- 松飾りやしめ飾りを片付ける「松の内」の地域差
- 新年の準備に役立つ贈り物のアイデア
松飾りいつから飾る?基本知識とルール
- 玄関の正月飾りいつからが最適か
- しめ縄や鏡餅はいつ飾るのですか?
- 正月飾りを飾っちゃいけない日はいつですか?
- 守りたいお正月飾りのルール
- 松飾りの飾り方のポイント
玄関の正月飾りいつからが最適か

お正月の玄関飾り、特に松飾りやしめ飾りをいつから飾るかについては、伝統的なルールが存在します。最も基本となるのは、12月13日の「正月事始め(しょうがつごとはじめ)」です。
この日は、かつて山へお正月に必要な薪や、門松にするための松の木を採りに行く「松迎え(まつむかえ)」という習慣があった日です。つまり、年神様をお迎えするための準備を開始する日とされており、この日以降であればいつ飾り始めても良いとされています。神社などでもこの日に「すす払い」を行うところが多くあります。
とはいえ、現代の一般家庭では13日から飾り始めるのは少し早すぎると感じるかもしれません。多くの場合、クリスマスツリーなどの片付けが終わる12月26日や27日頃から飾り始める方が多いようです。年末の大掃除を終え、家全体が清められた状態で新しいお飾りを設置するのが、気持ちの上でもすっきりしますね。
飾るのに最も縁起が良い日:12月28日
もし飾る日に迷ったら、12月28日を強くおすすめします。28日は、漢数字の「八」が「末広がり」を意味し、非常に縁起が良い日とされているためです。新年の幸運や繁栄を願うお飾りを設置するには、まさに最適な日取りと言えるでしょう。
逆に、避けるべき日(29日、31日)があるため、28日までに間に合わない場合は、キリが良い30日に飾るのが次善の策とされています。
しめ縄や鏡餅はいつ飾るのですか?

しめ縄(しめ飾り)や鏡餅も、松飾り(門松)と同様に、年神様をお迎えするための大切なお正月飾りです。そのため、飾り始める時期も松飾りと基本的に同じと考えて問題ありません。
前述の通り、12月13日の「正月事始め」以降であれば、いつ飾っても構いません。現実的なタイミングとしては、クリスマスが過ぎた26日頃から、縁起の良い28日、または30日までに飾るのがよいでしょう。
もちろん、これらのお飾りも29日(二重苦)と31日(一夜飾り)は避けるのが賢明です。
しめ飾りと鏡餅、それぞれの役割
お正月飾りは、それぞれに重要な意味が込められています。
- しめ飾り(しめ縄)
神社のしめ縄が神域を示すごとく、「神聖な場所(神域)と現世をへだてる結界」としての意味があります。玄関に飾ることで、家の中が年神様をお迎えするのにふさわしい清浄な場所であることを示し、魔除けや不浄なものが入るのを防ぐ役割を果たします。 - 鏡餅
年神様へのお供え物であると同時に、お正月の間に神様が宿られる「依り代(よりしろ)」です。古来、お米には霊力が宿るとされ、それを撞き固めたお餅は神聖な食べ物と考えられてきました。鏡餅を飾ることは、年神様に滞在していただく場所を提供するという意味があります。
どちらも松飾り(門松=目印)と合わせて、年神様をお迎えし、滞在していただくために欠かせない大切な3点セットです。
正月飾りを飾っちゃいけない日はいつですか?

お正月飾りを飾る日取りには、古くからの習わしとして「この日だけは避けるべき」とされる日が2日間あります。それは12月29日と12月31日です。
この日に飾ることは、縁起が悪い、または神様に対して失礼にあたると考えられています。
避けるべき日:12月29日と31日
12月29日
「九」の音が「苦」に通じるため、「二重苦(にじゅうく)」を連想させるとされています。また、「苦松(くまつ)=苦労を待つ」や「苦餅(くもち)=苦労を持つ」といった語呂合わせもあり、新年の幸運を願うお飾りを立てる日としては最も忌み嫌われる日です。
12月31日
大晦日、つまり元旦の前日になって慌てて飾ることを「一夜飾り(いちやかざり)」と呼びます。これは、十分な準備期間を設けず、たった一日だけ飾ることで、年神様をお迎えする誠意が足りないとされています。また、葬儀の準備が慌ただしく一日(一夜)で行われることと同じであるため、縁起が悪いとも言われています。
時の流れは早いもので、年末の忙しさに紛れてうっかり飾りそびれてしまうこともあるかもしれません。しかし、年神様に敬意を払い、良い新年を迎えるためにも、遅くとも12月30日までには飾り終えるよう意識することが大切です。
守りたいお正月飾りのルール

お正月飾りは、単なる季節のデコレーションではなく、年の初めに各家庭を訪れ、その年の幸運や実り(年齢)を授けてくださる「年神様」をお迎えするための大切な準備です。基本的な意味やルールを理解して、正しく飾りましょう。
代表的なお正月飾りには、主に以下の3つの役割があります。これらは年神様をお迎えするための「3点セット」とも言えます。
| お飾りの種類 | 主な意味・役割 | 飾る場所の例 |
|---|---|---|
| 門松(松飾り) | 年神様が家に来るための「目印(ランドマーク)」 | 玄関の門やドアの両脇 |
| しめ飾り | 神聖な場所を示す「結界(バリア)」 | 玄関の軒下、ドア、神棚 |
| 鏡餅 | 年神様が宿る「依り代(よりしろ)」 | 神棚、床の間、リビング |
特にマンションやアパートにお住まいの場合、玄関ドアの外側は「共用部分」にあたるため、消防法や管理規約によってお飾りを飾ることが禁止されているケースも少なくありません。必ず事前に規約を確認しましょう。
もし外側に飾れない場合は、玄関ドアの内側に飾っても全く問題ありません。神棚や床の間がないご家庭では、リビングのテーブルや棚の上など、家族が集まる清浄な場所に飾るのが良いでしょう。その際、鏡餅は玄関からできるだけ離れた、静かで奥まった場所に飾るのが良いとされています。
大切なのは、年神様をお迎えし、おもてなしするという感謝の気持ちです。ご自身の住環境に合わせて、無理のない範囲で丁寧に飾りましょう。
松飾りの飾り方のポイント

松飾りは、一般的に「門松」として知られ、年神様が家々に降臨される際の目印(アンテナ)となる非常に重要な役割を持っています。もともとは「松飾り」と呼ばれ、松の枝だけで作られることもありました。
本来は、玄関の門や戸口の両脇に一対(二つ)で立てるのが正式な飾り方です。これは、神様が迷わず家を見つけられるようにするためです。
しかし、現代の住宅事情、特にマンションやアパートなどでは、伝統的な大きな門松を立てるスペースを確保するのは難しいでしょう。その場合は、以下のような現代的な方法で代用するのがおすすめです。
現代の住宅に合わせた松飾りの飾り方
- 玄関ドアの内側に飾れる、ミニチュアサイズの門松を利用する。
- 松の枝や縁起物(南天、水引など)を使った壁掛けタイプの「松飾り」を玄関ドア(内側・または規約の範囲内で外側)に飾る。
- 最近では、ペーパーやフェルト素材、木製などで作られた、室内用のおしゃれな手作りキットやオブジェなども人気があります。
松と竹に込められた意味と「竹の切り口」
門松には、松だけでなく竹が使われることも多いです。これらにも縁起の良い意味が込められています。
- 松:冬でも緑を失わない常緑樹であることから、生命力や不老長寿の象徴とされています。
- 竹:成長が早く、まっすぐ天に向かってすくすくと伸びる姿から、長寿や繁栄の象徴とされています。
ちなみに、門松に使われる竹の切り口には2種類あるのをご存知でしょうか。
- そぎ:斜めに切ったもの。一説には徳川家康が使い始めたとされています。
- 寸胴(ずんどう):真横に(水平に)切ったもの。「口が開いていない」=「お金が逃げない」とされ、縁起が良いと考える向きもあり、主に銀行などで使われることが多いようです。
こちらの記事もオススメです(^^)/



松飾りはいつから片付ける?知識と新年準備
- 松飾りはいつからいつまで飾るのですか?
- お正月飾りは玄関でいつまで飾る?
- 2026年1月の鏡開きはいつですか?
- 新年の挨拶に最適な贈り物
- 自分へのご褒美も見つけよう
松飾りはいつからいつまで飾るのですか?

お正月飾りを飾っておく期間のことを「松の内(まつのうち)」と呼びます。文字通り「松(門松)を飾っておく内(期間)」という意味で、これは年神様が各家庭に滞在してくださっている期間を指します。
松飾りをはじめとするお正月飾り(鏡餅を除く)は、この松の内が明けたら(終わったら)片付けるのが一般的です。年神様をお見送りする、という意味合いがあります。
ただし、この「松の内」の期間は、お住まいの地域によって大きな違いがあるため注意が必要です。
松の内の期間(地域による違い)
松の内の期間は、大きく分けて以下の2パターンがあります。
- 1月7日まで:東北、関東、九州など多くの地方
- 1月15日まで:関西地方を中心としたエリア(例:大阪、京都、兵庫など)
もともとは全国的に1月15日(小正月)までだったとされています。しかし、江戸時代の1657年(明暦3年)に江戸で「明暦の大火」という大火事があり、燃えやすい松飾り(門松)が火の勢いを強めた一因とされました。この教訓から、幕府が「燃えやすい松飾りは早く片付けるように」と通達を出し、それがきっかけで関東を中心に松の内が1月7日までに短縮された、という説が有力です。(出典:神社本庁「お正月のまつり」)
最近では、テレビなどの影響で「七草がゆ(1月7日)を食べたらお正月も終わり」という認識が全国的にも広まりつつあります。しかし、本来は地域の習慣に従うのが最も丁寧な形です。ご自身のお住まいの地域がどちらの習慣なのか、一度確認してみると良いでしょう。
お正月飾りは玄関でいつまで飾る?

前述の通り、玄関に飾った松飾りやしめ飾りは、「松の内」の期間が過ぎたら片付けます。関東地方など多くの地域では1月7日、関西地方では1月15日が目安です。松の内が終わる日の夕方か、翌日の朝に片付けるのが一般的です。
片付ける際は、外したお飾りをどう処分するかにも大切なルールがあります。
最も丁寧な処分方法は、地域の神社や広場などで行われる「左義長(さぎちょう)」で燃やしてもらうことです。これは一般的に「どんど焼き」「とんど焼き」「鬼火焚き」など地域によって様々な呼び名があるお祭りで、お正月飾りや古いお札などを集めて燃やし、その炎と共に年神様を天にお見送りするという意味合いがあります。
どんど焼きに参加できない場合の処分方法
近くでどんど焼きが行われていない、または日程が合わずに参加できない場合は、家庭ゴミとして処分しても問題ありません。神様は事情を分かってくださるので、バチが当たるようなことはありません。
その際は、以下の手順で感謝の気持ちを込めて行いましょう。
- 新聞紙など、お飾りを包める大きさのきれいな紙を広げます。
- その上にお飾りを置きます。
- お清めの塩を「右・左・中」と振りかけ、清めます。
- 「一年間お守りいただきありがとうございました」と感謝の気持ちを込めながら、紙でお飾りを丁寧に包みます。
- 他のゴミとは別の袋に入れ、自治体のルールに従ってゴミに出します。(可燃ゴミで良いか、不燃物(針金など)を分別する必要があるか確認しましょう)
神社によっては「古札納所(こさつおさめしょ)」が常設されており、松の内が過ぎたお飾りを受け付けてくれる場合もあります。
2026年1月の鏡開きはいつですか?

松飾りやしめ飾りとは異なり、鏡餅だけは片付けるタイミングが異なります。年神様の依り代(よりしろ)であり、その魂(気力)が宿った神聖なお餅を下げて、家族で分けて食べる行事を「鏡開き(かがみびらき)」と呼びます。
2026年の鏡開きは、全国的には1月11日(日)に行うのが一般的です。
なぜ11日かというと、関東の松の内(7日)が明けた後、縁起の良い日としてこの日が選ばれたとされています。また、江戸時代の徳川幕府では、三代将軍・家光の月命日(20日)を避けて11日に行うようになったのが広まったという説もあります。
ただし、これも地域差があり、松の内が15日までの関西地方などでは、15日や20日に鏡開きを行うこともあります。
鏡開きの注意点:刃物はNG
鏡餅は、年神様の力が宿った神聖な食べ物です。それを刃物(包丁など)で切ることは、武士の「切腹」を連想させるため、縁起が悪いとして古くからタブーとされています。また、「良い縁を切る」ことにもつながると考えられています。
そのため、必ず「割る」という行為を行います。「割る」という言葉も縁起が悪いので、末広がりを意味する「開く」という縁起の良い言葉を使い、「鏡開き」と呼びます。
乾燥して固くなったお餅は、木づちなどで叩き割るか、水に浸けて柔らかくしてから手でちぎるようにしてください。割ったお餅は、お雑煮やおしるこ、かき餅などにして、年神様の力を分けていただき、家族の一年間の無病息災を願いましょう。
新年の挨拶に最適な贈り物

お正月の準備といえば、新年のご挨拶に持参する「お年賀」選びも欠かせません。お年賀とは、旧年中にお世話になったことへの感謝と、新年も変わらぬお付き合いをお願いしますというご挨拶の気持ちを込めて贈るギフトのことです。
その起源は、お正月に年神様を迎えるにあたり、神棚にお供え物(御歳魂)を持参した習慣が、次第に新年の挨拶回りの手土産に変わっていったものとされています。
お年賀を贈る時期は、本来は正月三が日(1月1日〜3日)に、相手の家を訪問して直接手渡しするのが正式なマナーです。しかし、現代では三が日に訪問するのが難しい場合も多いため、「松の内」(一般的には1月7日頃まで)に贈るのが良いとされています。(参考:小田急百貨店オンラインショッピングなど主要百貨店のギフトマナー参照)
もし松の内を過ぎてしまった場合は、表書きを「寒中御見舞」と変えて贈るのがマナーです。
相手別・おすすめのお年賀ギフト例
- 祖父母や親戚へ
新年の食卓が華やぐ高級かまぼこ(例:鈴廣の「松寿」「ちどり」)や、家族みんなで楽しめる高級スイーツ(例:ベジターレの「白金プラチナバウム」、CHOCOLATIER PALET D’ORの「獺祭ショコラ」)が喜ばれます。 - ご近所の方へ
相手に気を遣わせない程度の予算で、日持ちがして普段使いしやすい、おしゃれな調味料セット(例:mizunotoの「無添加おだしカクテル」、五代庵の「梅の調味料セット」)などが負担にならずおすすめです。 - 友人・知人へ
少し贅沢な気分を味わえるお酒のおつまみ(例:NICKJERKYの「ジャーキー3種」、燻製BALPALの「燻製ナチュラルチーズおつまみセット」)や、料亭の味(例:下鴨茶寮の「料亭のご馳走 楓」)も人気です。
金額の相場は相手によって異なりますが、あまり高価すぎるとかえって相手に気を遣わせてしまうため、2,000円〜5,000円程度が一般的です。
自分へのご褒美も見つけよう

年末年始は、大掃除や新年の準備、お客様のおもてなしなどで忙しく過ごす方も多いでしょう。慌ただしい時期を乗り越え、無事に新年を迎えたら、一年間頑張った自分へのご褒美も用意してみてはいかがでしょうか。
例えば、職人が魚一尾一尾を目利きして手作りする鈴廣の超特選かまぼこ「古今」や「古黄」は、全国かまぼこ品評会で最高賞を受賞するほどの逸品で、普段はなかなか手が出ない特別なご褒美にぴったりです。また、ドン・ペリニョンを使った大人のショコラアソートなども、新年の幕開けにふさわしい贅沢な味わいと言えます。
最近では、コロナ禍などを経て、年末年始に帰省がかなわない代わりに、会いたい気持ちや感謝を込めてギフトを贈る「帰歳暮(きせいぼ)」という新しいトレンドも生まれています。
家族で楽しめる鈴廣のおでんセットや、神戸ポークのハム・ソーセージアソート、食卓が華やぐ「海山のおーどぶる」などは、離れていても食卓を囲む温かい時間を共有するのに最適です。新年の贈り物選びは、お世話になった方へだけでなく、ご自身の頑張りをねぎらう機会としても活用してみてください。
松飾りはいつから準備すべきか総まとめ
最後に、この記事の要点をリストでまとめます。松飾りをいつから準備すべきか、いつ片付けるのか、そしてお正月の知識について振り返ってみましょう。
- お正月飾りは一年の初めに幸運を授ける年神様をお迎えするためのもの
- 松飾り(門松)は年神様が迷わず家に来るための「目印」
- しめ飾りは年神様が安心して来られる神聖な「結界」
- 鏡餅は年神様がお正月に滞在される「依り代」
- 飾り始めるのは12月13日の「正月事始め」以降ならいつでも良い
- 一般的にはクリスマス後の12月26日〜27日に飾ることが多い
- 最も縁起が良いとされる日は12月28日(末広がり)
- 12月29日は「二重苦(苦待つ)」で縁起が悪いので避ける
- 12月31日は「一夜飾り」で神様に失礼なので避ける
- 遅くとも12月30日までには飾り終えるのが望ましい
- 片付ける時期は年神様が滞在される「松の内」が明けてから
- 松の内は関東で1月7日、関西で1月15日が一般的(地域差あり)
- 処分は「どんど焼き(左義長)」で燃やし神様をお見送りするのが最良
- 家庭ゴミで出す場合は塩でお清めをし感謝を込めて別の袋で出す
- 鏡餅を片付けるのは「鏡開き」の日
- 鏡餅は刃物で切らず木づちなどで「開く」のがルール
- お年賀は松の内(1月7日頃まで)に贈るのがマナー
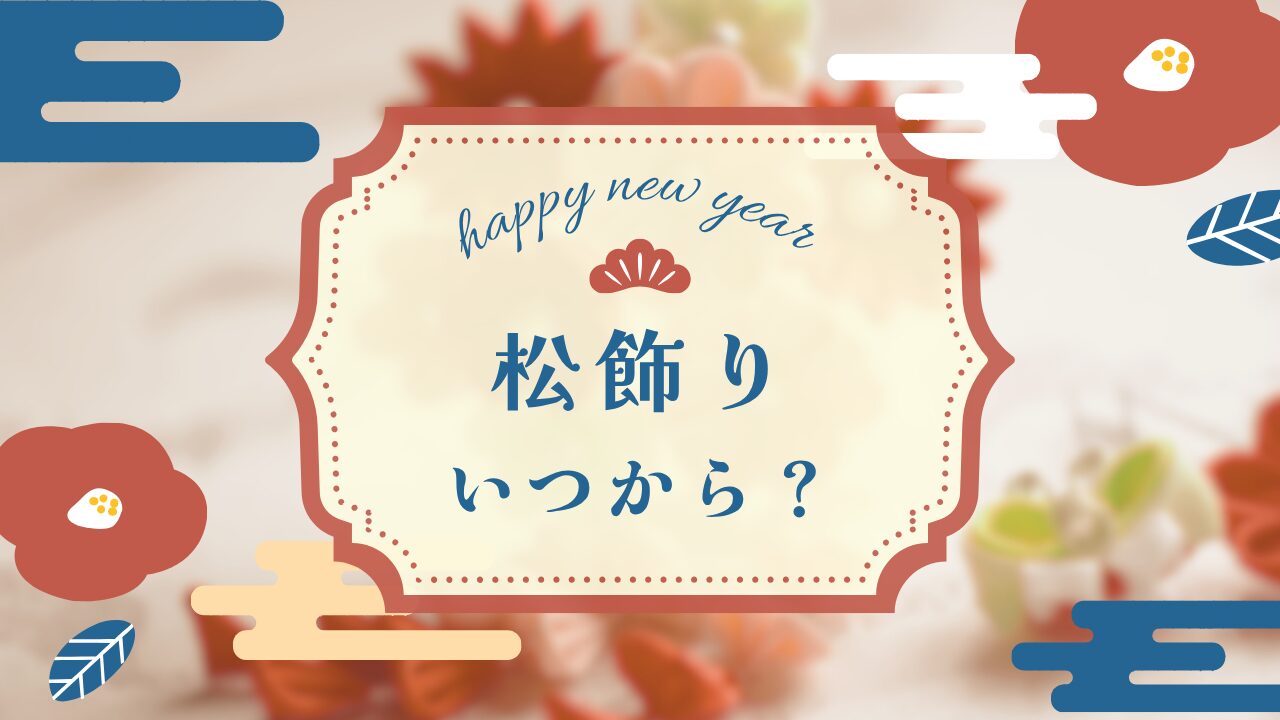


コメント