鏡開きは何時から?2026年の日程と地域別時間を解説
「鏡開きはいつやるのが正しいの?」「鏡開きって何時ごろから始めればいいの?」といった時間に関する疑問や、地域ごとの違いについて、あなたは混乱していませんか。お正月が終わるとやってくる鏡開きですが、そのやり方や食べ物、さらにはやってはいけないことなど、意外と知らないことが多いものです。特に関西や九州といった地域ごとの風習の違いや、10日や11日といった日付の具体的な理由まで知りたい方もいるでしょう。
この記事では、鏡開きなにする?という基本的な疑問から、よくある質問まで、あなたの知りたい情報を網羅的に、そして深く掘り下げて解説します。この記事を読めば、鏡開きに関するあらゆる悩みが解決し、日本の美しい伝統行事を心から楽しめるようになるはずです。
- 鏡開きの正しい日程と地域による違い
- 伝統的な鏡餅の割り方と現代的な方法
- 鏡開きにおけるタブーや注意点
- 年始の挨拶に喜ばれるお年賀の選び方
鏡開きは何時から?地域ごとの日程
- 2026年の鏡開きはいつですか?
- 関西など地域による違い
- 九州はいつ鏡開きをするの?
- そもそも鏡開きはいつおろすの?
- 鏡開き当日なにするのが一般的?
2026年の鏡開きはいつですか?

結論から言うと、2026年の鏡開きは、全国的には1月11日(日)が一般的な実施日となります。
鏡開きは、お正月に年神様をお迎えするために飾った鏡餅を、神様がお帰りになった後にお下がりとしていただく行事です。年神様が家に滞在される期間を「松の内」と呼び、関東を中心とする多くの地域ではこの松の内が1月7日までとされています。そのため、松の内が終わった後の縁起の良い日として、11日が鏡開きの日として定着しました。
2026年の1月11日は日曜日にあたるため、ご家族や親しい方々が集まりやすく、鏡開きを行うには最適な日と言えるでしょう。特に鏡開きを行う時間に「午前中でなければならない」といった厳密な決まりはありません。ご家庭のライフスタイルに合わせて、皆が揃う昼食や夕食の時間に行うのが一般的です。大切なのは、家族が揃って神様への感謝を共有することです。
2026年のポイント
多くの地域では1月11日の日曜日が鏡開きの日です。この日は休日ということもあり、時間を気にせずゆっくりと行事を行えます。家族の都合の良い時間帯を選び、新年の無病息災を願いましょう。
なぜ1月11日なの?
もともと鏡開きは1月20日に行われていました。しかし、徳川三代将軍・家光の月命日が20日であったことから、武家社会がこの日を避けるようになり、蔵開きの日にちである1月11日に変更されたという説が有力です。「11」という数字も縁起が良いとされ、広く一般に浸透していきました。
関西など地域による違い

鏡開きの日程は、実は全国一律ではありません。お住まいの地域によって風習が大きく異なるため、事前に確認することが大切です。特に、関東と関西では松の内の期間が違うため、鏡開きの日もはっきりと変わってきます。
この違いが生まれた背景には、江戸時代の歴史が関係しています。前述の通り、江戸幕府が松の内を1月7日までとするお触れを出した影響が、関東を中心に全国へ広まりました。しかし、農林水産省の解説する郷土料理にも見られるように、食文化に独自の伝統を持つ関西などの地域では、古くからの「松の内は15日まで」という風習が色濃く残り、幕府の方針が浸透しなかったとされています。
地域別・鏡開きの日程目安
以下に、地域ごとの一般的な鏡開きの日程を、より詳しくまとめました。ご自身の地域の習慣を確認する際の参考にしてください。
| 地域 | 一般的な鏡開きの日 | 背景・特徴 |
|---|---|---|
| 関東・東北・九州など | 1月11日 | 江戸幕府の政策により松の内が1月7日までとされた影響が強い地域です。 |
| 関西地方 | 1月15日 | 古来の風習が根強く、松の内を1月15日までとするため、その当日に行われます。 |
| 京都府の一部・周辺地域 | 1月4日または1月20日 | 「二十日正月(はつかしょうがつ)」として1月20日に行う他、商家などでは仕事始めの4日に行う独自の文化も見られます。 |
「二十日正月」は、正月の祝い事を締めくくる最後の日とされています。この日に鏡餅を食べることで、正月行事を滞りなく終えたことを意味します。格式を重んじる京都らしい風習と言えるでしょう。
このように、お住まいの地域によって日程は様々です。もしご自身の地域の慣習が不明な場合は、ご家族の年長者や、地域に古くから住んでいる方に尋ねてみるのが最も確実な方法です。

九州はいつ鏡開きをするの?

九州地方における鏡開きは、大部分の地域で関東などと同じく1月11日に行われるのが一般的です。
これは、歴史的に江戸との経済的・文化的交流が盛んであった地域が多く、江戸幕府の定めた慣習が比較的スムーズに浸透したためと考えられています。福岡、熊本、鹿児島といった主要都市圏では、松の内を1月7日までとし、その後の1月11日に鏡開きを行うのが通例となっています。
ただし、九州は7県からなる広大な地域であり、文化も多様です。山間部の一部の集落や、古くからの伝統を厳格に守る旧家などでは、関西式に1月15日や20日に行う独自の風習が今もなお残っている可能性は十分にあります。例えば、京都の文化の影響を受けた地域や、独自の歴史的背景を持つ場所では、周囲とは異なる日程を採用していることも考えられます。
もし九州地方にご実家があったり、移り住んだりして、ご自身の家庭の鏡開きの日程がはっきりしない場合は、まずはご家族や親戚に確認してみることを強くおすすめします。地域の風習や家庭の伝統を尊重することが、行事をより意義深いものにしてくれますよ。
そもそも鏡開きはいつおろすの?

鏡開きで鏡餅をおろすタイミングについて、最も重要な原則は「松の内」が明けてからという点です。
「松の内」とは、門松やしめ縄といったお正月飾りを飾っておく期間を指し、その語源は、年神様が依り代(よりしろ)である松に滞在される期間という意味に由来します。この期間中、年神様は各家庭に福をもたらすために留まっておられると信じられています。そのため、神聖なお供え物である鏡餅を、神様がいらっしゃる間に下げてしまうのは大変失礼にあたると考えられてきました。神様が天にお帰りになる松の内が明けた後、感謝を込めてそのお下がりをいただくのが鏡開きなのです。
松の内の期間が日付の違いを生む根本原因
前述の通り、この「松の内」の期間が地域によって異なることが、鏡開きの日付の差を生む根本的な原因となっています。
- 関東地方など(松の内が1月7日まで)
→ 7日に松飾りを片付け(七草がゆを食べる)、年神様をお見送りした後、11日に鏡開きを行います。 - 関西地方など(松の内が1月15日まで)
→ 15日までを松の内(小正月)とし、その当日または20日に鏡開きを行います。
つまり、「鏡開きをいつおろすか?」という問いへの最も的確な答えは、「地域や家庭の慣習における松の内が終わった後」となります。この一連の流れを理解することで、単なる日付の暗記ではなく、行事が持つ意味をより深く感じられるでしょう。

鏡開き当日なにするのが一般的?

鏡開き当日は、お正月の間、神棚や床の間にお供えしていた鏡餅を下げ、家族で分け合って食べるのが中心的な習わしです。
この行事は、単にお正月に飾ったお餅を消費するという意味合いではありません。鏡餅は年神様の力が宿る神聖な「依り代」とされています。それを家族でいただくことで、神様から新しい生命力や福を分けていただき、一年間の無病息災や家内安全を願うという、非常に重要な意味が込められています。この考え方は、硬いお餅を食べて歯を丈夫にし、長寿を願う「歯固めの儀」という平安時代からの風習にも通じています。
当日の一般的な流れは以下の通りです。
鏡開きの一般的な流れ
- 鏡餅を下げる
神様への感謝を口にしながら、お供えしていた場所から丁寧に鏡餅を下ろします。 - 鏡餅を開く
後述する正しい作法に則り、木槌や手で鏡餅を適当な大きさに分けます。 - 調理する
開いたお餅をお汁粉やぜんざい、お雑煮などの料理にします。 - 家族でいただく
家族全員が集まり、一年の健康や幸せを語り合いながら、感謝の気持ちを持っていただきます。
現代において鏡開きは、家族の絆を再確認し、深める絶好の機会でもあります。忙しい日常ではなかなか持てない家族団らんの時間を創出し、新年の抱負を語り合うことで、素晴らしい一年のスタートを切ることができるでしょう。
こちらの記事もオススメです(^^)/


鏡開きは何時から?やり方と贈り物
- 鏡餅の正しいやり方を解説
- 鏡開きでやってはいけないこと
- 鏡開きの日に食べる食べ物
- お歳暮との違いについて
- 新年の挨拶にオススメお年賀
鏡餅の正しいやり方を解説

鏡餅を「開く」際には、縁起を担ぎ、神様への敬意を示すための伝統的な作法があります。一方で、現代の生活様式に合わせた便利な方法も広く受け入れられています。それぞれの方法を詳しく解説します。
伝統的なやり方:木槌で「開く」
古くからの最も正式なやり方は、刃物を一切使わずに、木槌(きづち)や金槌、あるいは手で割る方法です。
この作法は、鏡開きの起源が武家社会の「具足開き(ぐそくびらき)」という、新年に甲冑にお供えした餅を食べて出陣を祝った儀式にあるためです。武士にとって刃物で「切る」という行為は「切腹」を強く連想させ、大変な禁忌とされていました。そのため、縁起の悪い「割る」や「切る」という言葉を避け、未来を切り開くという意味合いを持つ縁起の良い言葉「開く」を使い、木槌などで叩き分けるようになったのです。
お供えしている間に十分に乾燥し、ひびが入るほど硬くなった鏡餅は、木槌で叩くと比較的簡単に割れます。金槌を使う場合は、餅の破片が勢いよく飛び散ることがあるため、布や新聞紙で全体を覆ってから叩くと安全です。
現代的なやり方:手軽に柔らかくする
近年の気密性の高い住宅ではお餅が乾燥しにくかったり、カビ防止のために真空パックされた鏡餅が主流だったりするため、伝統的な方法が難しい場面も増えています。その際は、無理せず以下のような現代的な方法を取り入れるのが賢明です。
- 水に浸して柔らかくする方法
大きめのボウルや鍋に鏡餅を入れ、全体が浸るくらいの水に半日~一晩浸けておきます。すると、お餅が水分を吸って柔らかくなり、手で簡単にちぎれるようになります。 - 電子レンジで加熱する方法
耐熱皿に鏡餅を乗せ、お餅が少し湿る程度の水を加えます。その後、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ(600W)で30秒~1分ずつ、様子を見ながら加熱します。加熱しすぎるとお餅が溶けて器に張り付いてしまうため、少し硬さが残る程度で止めるのがコツです。
どの方法を選ぶにせよ、最も大切なのは、年神様からいただいた福を分かち合うという感謝の気持ちです。ご家庭の状況に合わせて最適な方法を選び、丁寧に扱いましょう。
鏡開きでやってはいけないこと

一年の始まりに福を招くための縁起の良い行事、鏡開き。しかし、そのやり方を間違えると、かえって運気を下げてしまうとされるタブー(やってはいけないこと)が存在します。知らず知らずのうちに不作法を行ってしまわないよう、ここでしっかりと確認しておきましょう。
鏡開きで絶対に避けるべき三大タブー
- 【禁忌】刃物で切る
前述の通り、包丁やナイフなどの刃物で鏡餅を切ることは最大のタブーです。これは武家社会の「切腹」を連想させるだけでなく、「神様との縁を切る」「家族の縁を切る」という意味にも繋がり、非常に縁起が悪いとされています。必ず手や木槌で「開く」ことを徹底してください。 - 【時期】松の内が明ける前に食べる
年神様がご自宅に滞在されている松の内の期間中に、お供え物である鏡餅を下げて食べるのは、神様に対して大変失礼な行為と見なされます。神様をきちんとお見送りした後に、感謝を込めていただくのが正しい順序です。 - 【扱い】食べ残したり捨てたりする
年神様の力が宿った神聖なお餅は、福そのものです。これを食べ残したり、安易に捨てたりするのは、いただいた福を自ら手放すのと同じことと考えられています。もし一度に食べきれない場合は、小さく分けて冷凍保存するなど工夫し、最後まで感謝していただくのが大切なマナーです。(保存方法はサトウ食品公式サイトなども参考にすると良いでしょう)
これらの注意点をしっかりと守り、年神様からのご利益を余すことなくいただいて、気持ちよく一年をスタートさせましょう。
鏡開きの日に食べる食べ物

鏡開きで開いたお餅は、様々な料理で美味しくいただくことができます。その食べ方には地域性や家庭の伝統が色濃く反映されますが、ここでは代表的で人気のある食べ物をいくつか詳しくご紹介します。
お汁粉・ぜんざい
鏡開きのお餅の食べ方として、最もポピュラーなのがお汁粉やぜんざいでしょう。甘く煮た小豆と、香ばしく焼いたお餅の組み合わせは、寒い季節に心と体を温めてくれる最高のデザートです。古くから小豆の赤色には魔除けや邪気を払う力があると信じられており、新年の無病息災を願う鏡開きの食べ物として、まさにうってつけと言えます。
「お汁粉」と「ぜんざい」の違いは?
一般的に、関東ではこし餡を使った汁気のあるものを「お汁粉」、粒餡を使った汁気の少ないものを「田舎汁粉」や「ぜんざい」と呼び分けます。一方、関西では粒餡を使った汁物全般を「ぜんざい」と呼び、こし餡のものを「お汁粉」と区別することが多いようです。
お雑煮
お正月の三が日に食べたお雑煮を、鏡餅を使って再び楽しむのも定番です。関西地方では、鏡開きのお餅は白味噌仕立てのお雑煮に入れるのが一般的です。三が日のものとは具材や味付けを少し変えてみることで、新たな気分で楽しむことができます。
かき餅・揚げ餅
しっかりと乾燥して硬くなった鏡餅の破片は、油で揚げると香ばしい「かき餅(揚げ餅)」に変身します。低温の油でじっくりと揚げるのが、サクサクに仕上げるコツです。塩や青のり、カレー粉、砂糖醤油など、お好みの味付けで楽しめば、大人のおつまみから子供のおやつまで幅広く活躍します。
まだまだある!アレンジレシピ
その他にも、お餅の活用法は無限大です。小さく切ったお餅と野菜をホワイトソースで和え、チーズを乗せて焼く「餅グラタン」や、ピザソースと具材を乗せて焼く「餅ピザ」も人気です。家族の好みに合わせて、様々なアレンジを試してみてはいかがでしょうか。

お歳暮との違いについて

年末年始は、日頃お世話になっている方へ感謝を伝える贈答の機会が増えます。その代表格が「お歳暮」と「お年賀」ですが、この二つの違いを正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。鏡開きの時期に話題にのぼることもある「お年賀」への理解を深めるため、お歳暮との違いを起源も交えて解説します。
最も大きな違いは、お歳暮が「一年の感謝を伝える年末の贈り物」であるのに対し、お年賀は「新年の挨拶を目的とした年始の贈り物」である点です。
| 項目 | お歳暮 | お年賀 |
|---|---|---|
| 目的・意味 | 一年の感謝を伝える。「歳暮」は年の暮れを意味する言葉。 | 新年の挨拶をする。旧年中の感謝と、新年も変わらぬお付き合いを願う。 |
| 贈る時期 | 12月上旬~25日頃までが一般的。 | 元日~松の内(関東では7日、関西では15日)まで。 |
| 渡し方のマナー | 年末の多忙な時期のため、配送で贈ることも一般的。 | 新年の挨拶に伺い、直接手渡しするのが正式なマナー。 |
| のし紙の表書き | 「御歳暮」 | 「御年賀」 |
鏡開きは松の内が明けてから行う行事ですので、お年賀を贈る時期とは少しずれていることになります。しかし、年始にお会いした方と「鏡開きはいつされますか?」といった会話になることは珍しくありません。こうした日本の贈答文化や季節の行事に関する知識は、円滑な人間関係を築く上での教養として、ぜひ身につけておきたいものです。
新年の挨拶にオススメお年賀

新年のご挨拶に伺う際に心を込めて持参するお年賀。相手に心から喜んでいただくためには、どのような品物を選べばよいのでしょうか。高価すぎるものはかえって相手に気を遣わせてしまうため、予算は3,000円~5,000円程度で、日持ちがして分けやすい、いわゆる「消えもの」が一般的です。
ここでは、定番でありながらもセンスが光る、オススメのお年賀の具体例をいくつかご紹介します。
個包装で華やかな焼き菓子
クッキーやフィナンシェ、バームクーヘンといった焼き菓子の詰め合わせは、日持ちがするため、贈る相手の都合をあまり気にしなくてよいのが最大のメリットです。個包装されていれば、家族や職場で分けやすい点も喜ばれます。お正月らしい干支をモチーフにした限定パッケージのものや、有名パティスリーの品を選ぶと、特別感が演出できます。
老舗の品格が伝わる和菓子
ご年配の方や、日頃から特にお世話になっている目上の方への贈り物としては、老舗の和菓子が最適です。格式高い羊羹や、縁起の良い形をした最中、色鮮やかな上生菓子などは、見た目にも美しく、感謝と敬意の気持ちを雄弁に伝えてくれます。
少し贅沢な飲み物のセット
普段は自分ではなかなか買わないような、少し贅沢な飲み物も気の利いた贈り物です。例えば、有名産地の果汁100%ストレートジュースのセットはお子様のいるご家庭に、名高い茶園の煎茶や玉露のセットはご年配のご夫婦に、といった形で相手の家族構成や好みに合わせて選ぶと、より一層喜ばれるでしょう。
もし相手の好みが全く分からない場合は、好きなものを選んでもらえるカタログギフトという選択肢もあります。近年ではお年賀用のカタログギフトも充実しており、失敗のない贈り物として人気が高まっていますよ。
お年賀を贈る際の注意点
相手方またはご自身が喪中の場合は、「おめでとう」という意味合いを持つお年賀を贈るのはマナー違反です。その場合は、松の内が明けてから「寒中御見舞」として贈るのが正しい作法となります。
鏡開きは何時からか総まとめ
この記事では、鏡開きの正しい時間や日程、地域ごとの違いから、具体的なやり方、そして関連する贈答マナーまで、幅広く詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをリスト形式で振り返ります。
- 2026年の鏡開きは全国的に1月11日(日)が一般的
- 鏡開きを行う時間に厳密な決まりはないが家族が集まる時間が望ましい
- 関西では1月15日、京都の一部では1月20日に行うなど地域差がある
- 九州地方の鏡開きは一般的に1月11日が多いが家庭の慣習も確認する
- 鏡餅は年神様が帰る「松の内」が明けてからおろすのが鉄則
- 松の内の期間が関東は7日まで、関西は15日までと違うことが日付の差の理由
- 鏡開きは年神様の力が宿った餅を食べ一年間の無病息災を願う神聖な行事
- 伝統的なやり方では刃物を使わず「切腹」を避けるため木槌などで「開く」
- 現代では水に浸したり電子レンジで柔らかくする方法も便利で実用的
- 刃物で「切る」ことは縁起が悪いため最大のタブーとされる
- 松の内が明ける前のフライングや、いただいた福を食べ残すことも避けるべき
- 食べ方としてはお汁粉やぜんざい、お雑煮が定番で人気がある
- お歳暮は年末の感謝、お年賀は年始の挨拶という目的と時期に明確な違いがある
- お年賀は日持ちのするお菓子や飲み物が定番で喜ばれやすい
- 鏡開きは日本の伝統文化と家族の絆を再確認する良い機会となる
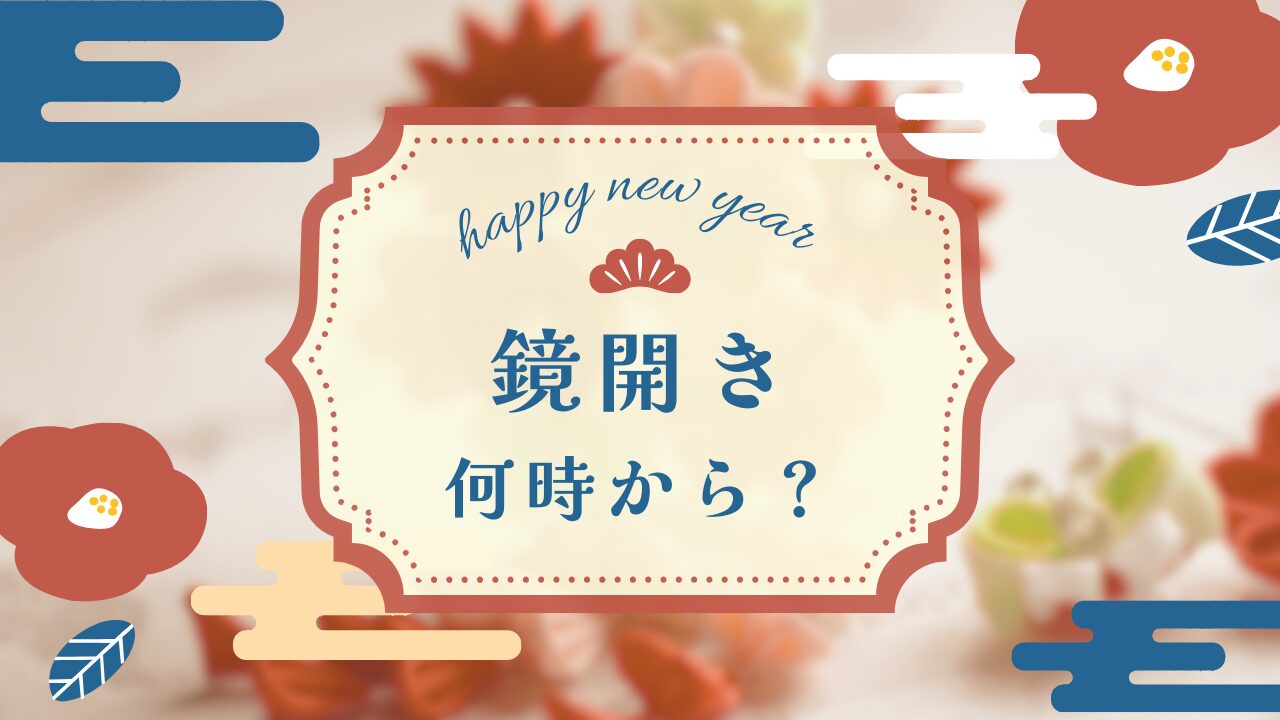


コメント