親からの結婚祝いのお返し|相場・マナーとおすすめギフト完全ガイド
ご結婚おめでとうございます。親からの結婚祝いという、心温まるサポートを受け取り、「お返しは本当に必要なのだろうか」「いくらくらいの品物を贈れば失礼にならないか」といった、嬉しくも悩ましい疑問をお持ちではないでしょうか。両親や、これから本当の家族になる義両親への内祝いは、単なる「お返し」という言葉では片付けられない、深い意味を持つものです。
それは、これまで育ててくれた日々への感謝を形にし、これから夫婦として歩む未来への良好な関係を築くための、大切なコミュニケーションに他なりません。
この記事では、親からの結婚祝いに対するお返しの基本マナーから、具体的な金額の相場、相手の好みが分からなくても安心なカタログギフトの選び方、さらには見落としがちながら非常に重要な義両親へのお礼メールの書き方まで、皆さまが抱えるよくある質問に、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。
この記事でわかること
- 親への結婚内祝いの必要性と本質的な意味
- いただいた金額別に解説する適切なお返しの相場
- 両親・義両親に心から喜んでもらえるギフトの選び方
- 感謝の気持ちがしっかりと伝わるメッセージやお礼メールの書き方
親からの結婚祝い お返しの基本マナーと相場
- 両親から結婚祝いをもらったらお返しは必要ですか?
- みんなは結婚祝いを親からいくらもらった?
- 結婚内祝いで両親からいらないと言われた場合
- 親から10万円の結婚祝いへのお返しはいくら?
- 30万円や50万の高額なお祝いへのお返し
両親から結婚祝いをもらったらお返しは必要ですか?

結論から申し上げますと、両親から結婚祝いをいただいたら、お返し(内祝い)は必ず贈りましょう。これは、ご自身の両親であっても、パートナーの両親(義両親)であっても、等しく大切にすべき基本的なマナーです。
結婚祝いをいただく際に「私たちのことは気にしないで。お返しは要らないからね」と言葉をかけられるケースは非常に多いものです。しかし、それは子を想う親の優しさであり、その言葉を額面通りに受け取ってしまうのは避けたいところです。両親からの「要らない」という言葉の裏には、「ふたりの新しい生活のために、そのお金を有効に使ってほしい」という深い愛情が込められています。その温かい気持ちに心から感謝しつつも、結婚という人生の大きな節目に、改めて「ありがとう」を伝える社会人としてのけじめとして内祝いを贈ることが、これまで以上に成熟した、良好な親子関係を築く上でとても大切になります。
言ってしまえば、結婚内祝いは単なる返礼品ではありません。これまで無償の愛で育ててくれたことへの感謝、そして「これからは二人で力を合わせて、温かい家庭を築いていきます」という決意表明を示すための、またとない絶好の機会なのです。
義両親との未来の関係づくりの第一歩
特にパートナーの両親(義両親)との関係は、結婚当初の対応がその後の長いお付き合いの土台を築きます。結婚祝いは新郎新婦「ふたり」に贈られるものですから、感謝の気持ちをきちんと形にして示すことで、「礼儀をわきまえた、しっかりした人だ」という信頼感につながります。この最初の小さな心遣いが、今後の円満な関係を育む大きな一歩となるのです。
みんなは結婚祝いを親からいくらもらった?

親からいただく結婚祝いの金額は、それぞれの家庭の考え方や地域の慣習、経済状況によって大きく異なり、一概に「これが正解」という決まった金額はありません。しかし、一般的な相場を知っておくことで、自分たちがどの程度の支援を受けたのかを客観的に把握し、お返しの予算を立てる上での重要な指針とすることができます。
株式会社リクルートが発表した「ゼクシィ結婚トレンド調査2023(首都圏版)」によると、親・親族から結婚式の費用として援助があったカップルは全体の78.7%にのぼり、その援助総額の平均は181.7万円という結果が出ています。これはあくまで費用援助の平均ですが、結婚という一大イベントに対して、親が大きくサポートする傾向がうかがえます。
一方で、結婚式の費用援助とは別に、ご祝儀としてお祝いをいただくケースも多く、その場合は10万円~30万円程度が一般的な相場と言われています。
親からの結婚祝い 金額相場(目安)
| 援助の形式 | 金額の目安 | 背景・目的 |
|---|---|---|
| ご祝儀として(費用援助なし) | 10万円~30万円 | 新生活の準備資金や門出を祝う純粋なお祝い |
| 結婚式費用の一部として | 50万円~150万円以上 | 挙式費用、披露宴費用、衣装代などの具体的な費用負担 |
このように、いただく金額には家庭によって大きな幅があります。最も大切なのは、金額の大小に一喜一憂することなく、ふたりの門出を心から祝ってくれる親の深い愛情に感謝することです。いただいた金額は夫婦間で隠さずしっかりと共有し、それをもとに感謝の気持ちをどう形にするか、お返しの予算を丁寧に話し合うようにしましょう。
結婚内祝いで両親からいらないと言われた場合

両親から「お返しは本当にいらないから」と強く念を押された場合、どう対応すべきか非常に迷いますよね。前述の通り、言葉通りに何もしないのは避けたいものですが、一方で高価な品物を贈って「だから要らないと言ったのに」と気を遣わせてしまうのも本意ではありません。
このようなデリケートな状況では、相場よりも少し控えめな金額の品物をスマートに贈るか、「内祝い」という形式にこだわらず別の形で感謝を伝えるのがおすすめです。
具体的には、以下のような方法が心に響くでしょう。
少額の内祝いに心を込めた手紙を添える
相場の3分の1よりもさらに少ない1万円未満の予算で、少し高級なお菓子やこだわりのグルメギフトを選び、そこに直筆の心のこもった手紙を添えて贈る方法です。品物以上に、手紙という形に残る感謝の言葉が、何よりの贈り物になるでしょう。「品物だけだと受け取ってもらえないかもしれない」という心配がある場合に特に有効な手段です。
新婚旅行のお土産を奮発して特別感を演出する
「内祝い」という堅苦しい形にこだわらず、新婚旅行のお土産を少し豪華にするのも非常に良いアイデアです。現地の特産品や有名なお酒、工芸品など、両親の趣味や好みに合わせた特別な一品を選び、「結婚祝いのお礼も兼ねて、ふたりで選びました」と一言添えて渡せば、相手も気兼ねなく自然な形で受け取ってくれるはずです。
食事会に招待し、ふたりの時間そのものを贈る
新居に両親を招いて、感謝を込めて手料理をふるまったり、少し高級なレストランで食事会を開いたりするのも、大変喜ばれる感謝の伝え方です。特に、ふたりが新しい生活で仲良く、幸せに暮らしている姿を見せることが、何よりの親孝行となり、安心につながります。
パートナーの両親への配慮を絶対に忘れずに
ここで最も注意すべき点は、両家間の対応のバランスです。自分の親には「いらない」と言われたから何もしない、でもパートナーの親には内祝いを贈る、という対応は絶対に避けましょう。両家で対応に明確な差が出てしまうと、後々のトラブルや不信感の原因になりかねません。必ず夫婦で「両家ともに、ささやかながら食事会に招待しよう」といった方針を話し合い、両家へ同じように対応するのが、家族円満の最大の秘訣です。
親から10万円の結婚祝いへのお返しはいくら?

親から10万円という節目の金額で結婚祝いをいただいた場合、お返しの相場は3万円~5万円程度が一般的な目安となります。これは、古くからの慣習である、いただいた金額の「3分の1」から「半額(半返し)」に相当する金額です。
ただし、これはあくまで一般的なマナーに沿った形式的な金額であり、絶対的なルールではありません。特に両親からの高額なお祝いには「新生活の経済的な援助」という強い意味合いが込められているため、杓子定規に半額を返す必要はまったくないのです。むしろ、律儀に高額すぎるお返しをすると「私たちの気持ちを受け取ってもらえなかった」と、かえって寂しい思いをさせてしまう可能性すらあります。
両親の性格や家庭ごとの慣習を一番に考慮して、金額を柔軟に決めるのが最善策です。例えば、形式ばったことが苦手で実用性を重んじるご両親であれば3万円程度の美味しいグルメギフト、記念になるものを大切にするタイプであれば5万円程度の体験ギフトなど、予算内で最も喜んでもらえそうなものを夫婦で話し合って選びましょう。
もし予算設定に迷った場合は、3万円程度の品物を選び、それに加えて父の日や母の日、誕生日に少し良いプレゼントを贈ったり、帰省の際に食事に招待したりと、一度きりの高額なお返しではなく、継続的に感謝の気持ちを伝えていくという長期的な視点を持つことも非常におすすめです。
30万円や50万の高額なお祝いへのお返し

結婚式の費用援助などの形で、30万円や50万円、あるいはそれ以上といった高額なお祝いをいただいた場合、お返しの金額に頭を悩ませる方は少なくありません。セオリー通りに半返しをすると15万円~25万円となり、新生活をスタートさせたばかりの若い夫婦にとっては、現実的に大きな経済的負担になってしまいます。
このような高額なお祝いに対しては、相場にこだわる必要は一切ありません。むしろ、相場を気にして無理をすることのほうが、親の意図に反してしまうでしょう。
子を思う親心としては、「ふたりのために役立ててほしい」「少しでも負担を軽くしてあげたい」という気持ちが第一です。その温かい想いを素直に受け取り、お返しは3万円~5万円程度の、無理のない範囲で、感謝の気持ちが最大限に伝わる品物を選ぶのが最も賢明な判断です。10万円を超えるような高額なお返しは、かえって「そんなつもりじゃなかったのに」と余計な心配をかけてしまうことになりかねません。
大切なのは金額よりも「感謝の伝え方」です。高額な援助を受けた場合は、品物でのお返しに加えて、以下のような具体的な行動で誠意を見せることが、何よりも重要になります。
- 夫婦揃って直接お礼に伺う:電話やメールで済ませず、時間を作って訪問し、顔を見て感謝を伝えます。
- いただいたお金の使い道をきちんと報告する:「おかげさまで、希望していた素敵な家具が買えました。今度ぜひ見に来てください」など、具体的に報告することで、親は安心し、援助した喜びを感じることができます。
- 定期的に顔を見せ、元気な姿を報告する:こまめに連絡を取り、夫婦仲良く暮らしている様子を伝えることが、最高の恩返しになります。
このように、品物だけで感謝を完結させようとせず、その後の丁寧なコミュニケーションを通じて感謝を伝え続ける姿勢が、何よりも両親を喜ばせるお返しとなるのです。
こちらの記事もオススメです(^^)/
親からの結婚祝い お返しに喜ばれる品と贈り方
- 親族から100万円の結婚祝いへのお返しは?
- 義両親へのお礼メールで感謝を伝える方法
- 迷ったらコレ!人気のカタログギフトを紹介
- 親への内祝いで押さえておきたいよくある質問
親族から100万円の結婚祝いへのお返しは?

ご両親だけでなく、祖父母や叔父・叔母といった親しい親族から、100万円という非常に高額なお祝いをいただくケースもあります。このような場合のお返しも、基本的には相場通り(半返し~3分の1)である必要はありません。
親族からの高額なご祝儀には、ご両親同様に「新しい生活の支えになってほしい」という強い応援の気持ちが込められています。また、一族間の慣例として「自分たちも若い頃に親戚から援助してもらったから、今度は自分たちが返す番だ」という、一種の助け合いの精神が背景にあることも考えられます。
お返しの金額としては、5万円~10万円程度を目安に、感謝の気持ちを込めて質の高い品物を選ぶのが一般的です。もちろん、これはあくまで目安であり、無理のない範囲で、もう少し奮発しても構いません。最も大切なのは、いただいた金額に見合う高価なものを機械的に返すことではなく、相手を敬い、心からの感謝の気持ちをしっかりと伝えることです。
まず両親に相談するのが鉄則
親族から高額なお祝いをいただいた場合、ご夫婦だけでお返しを決める前に、必ず一度、ご自身の両親に相談することを強くおすすめします。親族間の付き合いには、その家ごとに暗黙のルールや過去の経緯が存在することが多々あります。「〇〇伯父さんには、これくらいの金額でお返しするのが我が家の慣例だよ」といった、貴重な情報を教えてもらえるかもしれません。こうした確認を怠ると、知らず知らずのうちにマナー違反を犯してしまう可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
品物としては、記念に残る置物や上質なペア食器、ご夫婦でゆっくりと楽しめる旅行券や高級レストランの食事券などが人気です。また、いただいたお金で新居の家具や家電を購入した場合は、その写真とともにお礼状を送ると、お金が有効に活用されたことが具体的に伝わり、贈った側も非常に喜ばしい気持ちになるでしょう。
義両親へのお礼メールで感謝を伝える方法

結婚祝いをいただいたら、後日品物でのお返し(内祝い)を贈ることはもちろんですが、それとは別にまずは迅速にお礼の気持ちを伝えるのが社会人としての重要なマナーです。特に義両親へは、タイミングを逃さず、かつ丁寧で誠実な対応を心がけたいものです。
お祝いを対面でいただいたのであればその場で深くお礼を述べ、郵送や銀行振込でいただいた場合は、受け取ったことを確認してから遅くとも当日か翌日には、まず電話で直接お礼を伝えましょう。声で感謝を伝えることで、気持ちがよりストレートに伝わります。その上で、改めてメールや手紙を送ると、さらに丁寧な印象を与え、礼儀正しい人という評価につながります。
ここでは、さまざまな状況ですぐに使えるお礼メールの文例と、好印象を与えるためのポイントをご紹介します。
義両親へのメール文例(基本形)
件名:結婚祝いのお礼([自分の名前]より)
お義父様、お義母様
本日、心のこもった結婚のお祝いを拝受いたしました。
私達二人のために、このような素晴らしいお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。〇〇さん(パートナーの名前)ともども、感激しております。
いただいたお祝いは、これからの新生活のために大切に使わせていただきます。
まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは〇〇さんと力を合わせ、お義父様とお義母様のような温かく、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思っております。
ささやかではございますが、後日改めてお礼の品をお贈りさせていただきますので、ご笑納いただけますと幸いです。
季節の変わり目ですので、どうぞご自愛くださいませ。
今後とも、末永くよろしくお願い申し上げます。
(自分の名前)より
お礼メールで好印象を与える5つのポイント
- 感謝の言葉を具体的に:まず何に対するお礼なのかを明確に伝えます。「素晴らしいお祝い」「温かいお心遣い」など、少し言葉を添えるだけで気持ちが伝わります。
- 必ず夫婦連名で:お祝いは「二人へ」のものです。「〇〇さんと二人で、大変喜んでおります」というように、パートナーと喜びを分かち合っているニュアンスを必ず入れましょう。
- 今後の抱負で敬意を示す:「お二人のような素敵な家庭を築きたい」といった一言は、義両親への尊敬の念を示すことになり、非常に喜ばれます。
- 内祝いを贈る旨を伝える:品物を別途贈ることを明確に伝えることで、メールだけで済ませる意図がないことを示し、誠実な印象を与えます。
- 結びの言葉で気遣いを:相手の健康を気遣う一文を入れることで、メール全体がより温かいものになります。
繰り返しになりますが、メールはあくまで取り急ぎのお礼です。後日、内祝いの品を直接お渡しする際や、品物に添える手紙で、改めて感謝の気持ちを伝えることが何よりも大切です。
迷ったらコレ!人気のカタログギフトを紹介
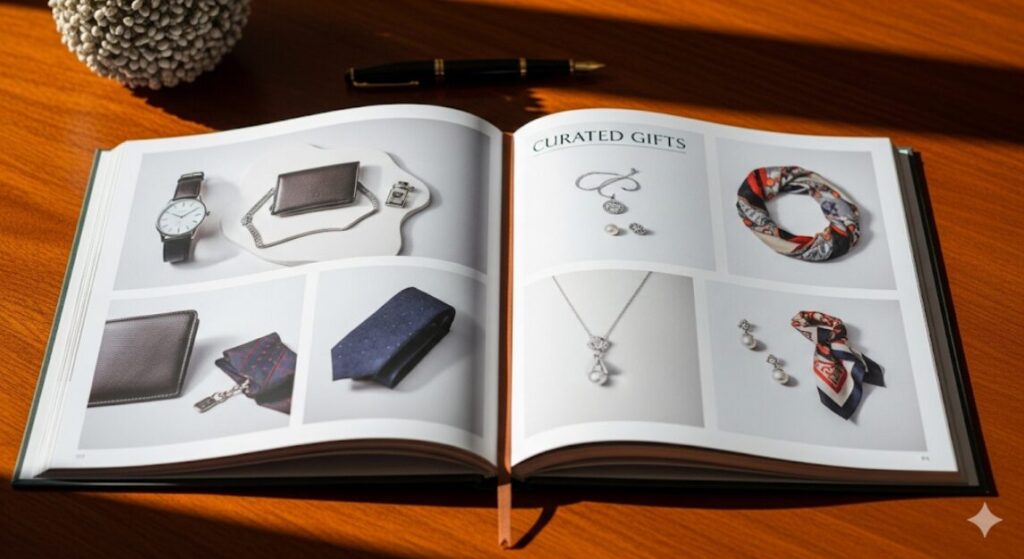
「両親の好みがはっきりと分からない」「義両親に失礼のない、間違いのないものを贈りたい」…そんなふうに内祝い選びで迷ったときに、非常に心強い味方となってくれるのがカタログギフトです。
カタログギフトの最大のメリットは、贈られた側が豊富な選択肢の中から本当に欲しいもの、必要なものを自分のペースで選べる点にあります。これにより、せっかく贈ったのに好みが合わずにがっかりさせてしまうという、贈り手として最も避けたい事態を防ぐことができます。近年では、単なる商品の羅列ではなく、特定のテーマやコンセプトに特化した、選ぶ時間そのものを楽しめるユニークなカタログギフトが増えています。
親世代に特に喜ばれるカタログギフトのジャンル
- グルメ専門カタログ:全国各地の知る人ぞ知るお取り寄せグルメや、有名レストランのスイーツ、A5ランクの高級和牛などが豊富に掲載されているカタログ。美味しいものが好きなご両親には間違いなく喜ばれます。
- 体験型カタログ:有名旅館での宿泊や都心の高級レストランでの食事、人間ドックの受診、伝統工芸体験、クルージングなど、「モノ」ではなく「特別な時間(トキ)」を贈るギフト。ご夫婦水入らずの、思い出に残る時間をプレゼントできます。
- 上質セレクトショップ系カタログ:BEAMSやUNITED ARROWSといった有名セレクトショップが監修した、デザイン性と品質の高い雑貨やファッションアイテムが揃うカタログ。センスが良く、おしゃれなご両親におすすめです。
- 専門誌コラボカタログ:婦人画報やdancyuといった、特定の分野で権威のある雑誌とコラボレーションしたカタログギフトも人気です。雑誌の編集部が厳選したこだわりの品々は、質を重視する親世代の満足度も高いでしょう。
カタログギフトを贈る際の注意点と心遣い
非常に便利なカタログギフトですが、いくつかの注意点も存在します。「たくさんの商品から選ぶのが面倒」「結局欲しいものがなかった」と感じる方も少数ながらいらっしゃるため、ご両親の性格を考慮して選ぶことが重要です。また、多くのカタログギフトには申し込みの有効期限が設定されています。期限が切れてしまうと無駄になってしまうため、贈る際に「半年ほどの期限があるから、ゆっくり選んでね」と一言伝えてあげると、より親切な対応になります。
もしカタログギフトだけでは少し味気ない、気持ちが伝わりにくいと感じる場合は、日持ちのする上質なお菓子や吸水性の良いタオルなど、ちょっとした品物をセットにして贈ると、ボリューム感も増し、より心のこもった温かい贈り物になります。
親への内祝いで押さえておきたいよくある質問

ここでは、両親への結婚内祝いに関して、多くの方が共通して疑問に思う点をQ&A形式で、より詳しく解説します。
Q1. 内祝いを贈るタイミングはいつがベスト?
A1. タイミングは非常に重要です。結婚式を挙げた場合は挙式後1ヶ月以内、入籍のみの場合はお祝いをいただいてから1ヶ月以内が一般的な目安とされています。結婚式後は新婚旅行や各種手続きで慌ただしくなるため、事前にリストアップしておき、式後すぐに手配できるように準備しておくとスムーズです。もし万が一、1ヶ月を過ぎてしまいそうな場合は、品物を送る前に電話で一報入れ、「お礼が遅くなり申し訳ありません」と伝えるのが丁寧な対応です。
Q2. 熨斗(のし)は絶対に必要?正しい書き方は?
A2. どれだけ親しい間柄であっても、内祝いに熨斗は必ずかけましょう。これが正式な贈答品であるという証になります。結婚に関するお祝い事は「一度きり」であることが望ましいため、水引は固く結ばれてほどけない「紅白または金銀の結び切り(10本)」を選びます。表書きは「内祝」または「寿」とし、署名(名入れ)は、夫婦の新しい姓のみ、または姓の下に二人の名前を右に夫、左に妻の順で連名で記載するのが一般的です。詳しくは、髙島屋のウェブサイトなど、ギフトのマナーを解説するページも参考にすると良いでしょう。
Q3. 内祝いで贈ってはいけないタブーな品物はある?
A3. はい、古くからの慣習で縁起が悪いとされる品物は避けるのが一般的です。例えば、「縁を切る」を連想させる刃物(包丁やハサミ)や、「手切れ(てぎれ)」を意味するハンカチ(漢字で「手巾」と書くため)、「苦」や「死」を思わせる櫛(くし)などがそれに当たります。また、相手を踏みつけることを意味する履物(靴下やスリッパ)や敷物(マット類)も、特に目上の方には避けた方が無難とされています。
Q4. 現金でお祝いをもらった場合、お返しも現金でいいの?
A4. いいえ、現金でお祝いをいただいた場合でも、お返しは必ず「品物」でするのが絶対的なマナーです。現金や金券(商品券など)でお返しをすると、いただいた金額が直接的に分かってしまい、相手に「お祝いをそのまま突き返された」という非常に失礼な印象を与えかねません。相手の好みやライフスタイル、家族構成などを考慮し、心を込めて選んだ品物を贈りましょう。それが贈り手としての礼儀です。
感謝が伝わる親からの結婚祝い お返し選び
- 親からの結婚祝いには「内祝い」としてお返しをするのが基本マナー
- 「いらない」という言葉に甘えず、何らかの形で感謝を示すことが大切
- 一般的なお祝いの相場はご祝儀で10万円から30万円程度
- 結婚式の費用援助の場合は50万円以上の高額になることもある
- お返しの相場はいただいた金額の3分の1から半額が基本的な目安
- 10万円のお祝いには3万円から5万円程度のお返しが一般的
- 30万円や50万円、100万円など高額な場合は相場にこだわる必要はない
- 高額祝いへのお返しは3万円から5万円程度の無理のない範囲で気持ちを伝える
- 品物選びに迷ったら相手が自由に選べるカタログギフトが便利で失敗がない
- グルメ専門や体験型など、相手の趣味に合わせたテーマ性のあるカタログが人気
- お祝いをいただいたら、まず電話やメールで当日か翌日中に迅速にお礼を伝える
- 特に義両親へのお礼メールは、今後の良好な関係を築く上で非常に重要
- 内祝いを贈る時期は、挙式後またはお祝いをいただいてから1ヶ月以内を目安に
- 贈る品物には必ず「紅白の結び切り」の熨斗をかけ、夫婦連名で名前を記す
- 刃物やハンカチ、履物など、縁起の悪いとされるタブーな品物は避ける



コメント