新年の挨拶何時まで?基本と手土産マナー
年始の挨拶で「あけましておめでとうございます」といつまで言ってよいのか、そのタイミングに迷った経験はございませんか。親しい間柄であれば多少くだけても許されるかもしれませんが、特にビジネスシーンでは、挨拶の時期を間違えるだけで少し気まずい雰囲気になってしまうこともあります。「新年の挨拶何時まで」という疑問は、社会人として正しいマナーを身につけたいと考える多くの方が抱く共通の悩みです。
この記事では、年始の挨拶の基本的な期間の解説から、ビジネスでスマートに使える短めのフレーズ、さらには訪問時に信頼を深める手土産や、感謝が伝わる心のこもった贈り物選びのポイントまで、深く掘り下げて詳しく解説します。この機会に、曖昧だった知識を確かなものに変え、自信を持って新しい一年をスタートさせましょう。
- 新年の挨拶をいつまですべきかが明確になる
- ビジネスシーンでの挨拶メールのマナーがわかる
- 挨拶が遅れた場合のスマートな対応方法が身につく
- 年始の挨拶に最適な手土産の選び方がわかる
新年の挨拶何時まで?知っておきたい基本マナー
- 新年の挨拶は何時までにすればいいですか?
- 新年のご挨拶はいつまでですか?【関西関東】
- 仕事での新年の挨拶、いつまでが適切か
- 新年の挨拶 ビジネスメールでの注意点
- 新年の挨拶が遅くなった場合のメール対応
- 新年の挨拶遅れたメールに使える例文
新年の挨拶は何時までにすればいいですか?

新年の祝賀を述べる「あけましておめでとうございます」という言葉は、古くからの慣習に則り、一般的に「松の内(まつのうち)」と呼ばれる期間が終わるまで使うのが正式なマナーとされています。この期間を過ぎてしまうと、お正月の特別な雰囲気が一段落したと見なされるため、新年の挨拶としては時期を逸した印象を与えてしまう可能性があります。
松の内とは、お正月にその年の豊穣や幸福をもたらす「年神様(としがみさま)」をお迎えし、おもてなしするために、家の玄関に門松やしめ飾りといった正月飾りを設置しておく期間を指します。つまり、年神様が各家庭に滞在されている神聖な期間であり、この間はまだ新年のお祝いムードが続いている、と考えると分かりやすいでしょう。この松の内が終わると、人々は正月飾りを取り払い(「松下ろし」とも言います)、日常生活へと戻っていくため、そこが一つの明確な区切りとなります。したがって、新年の挨拶もこの期間内に済ませるのが通例となっているのです。
ポイント
新年の挨拶は、神様をお迎えしている特別な期間である「松の内」まで、と覚えておくのが基本です。この期間を過ぎてから新年の挨拶をする場合は、後述するように挨拶の言葉自体を変えるといった配慮が求められます。
ただし、注意したいのは、この「松の内」がいつまでかという点については、実は日本国内で統一されておらず、地域によって違いが見られるという事実です。そのため、挨拶をする相手が住んでいる地域の慣習を事前に理解しておくと、より丁寧で心のこもった印象を与えることができるでしょう。
新年のご挨拶はいつまでですか?【関西関東】

前述の通り、新年の挨拶の目安となる「松の内」の期間は、地域によって慣習が異なります。特に、関東地方と関西地方では期間が大きく違うため、ビジネスやプライベートでの交流がある方はぜひ覚えておきたい知識です。一般的に、関東では1月7日まで、関西では1月15日までを松の内とするのが主流です。
なぜこのような違いが生まれたのかというと、その背景には江戸時代の幕府の通達が深く関係していると言われています。もともと全国的には、年の初めの満月の日である1月15日の「小正月(こしょうがつ)」までを松の内とするのが一般的でした。しかし、江戸幕府三代将軍・徳川家光が慶安4年(1651年)4月20日に亡くなったことから、月命日である20日の飾り物を避けるため、幕府がお飾りをしまう日を1月7日に定めたという説が有力です。これが城下町である江戸を中心に、「武家が発信した新しい習慣」として関東一円に広まっていきました。一方で、関西やその他の地域では、古くからの「小正月」を重んじる文化が根強く残り、1月15日までという慣習が維持された形です。
| 地域 | 期間 | 主な背景・文化 |
|---|---|---|
| 関東・東北・北海道・九州など | 1月7日まで | 江戸幕府の通達が由来とされる |
| 関西・東海・中国・四国など | 1月15日まで | 「小正月」までの伝統的な慣習が残る |
豆知識
どちらの期間に合わせるべきか迷った際は、短い方の「1月7日」までを基準に考えておけば、全国ほとんどの地域で失礼にあたることはありません。特に、ビジネスメールや年賀状など、相手の居住地が多岐にわたる場合は、7日を目安に行動するのが最も無難で安全な選択と言えるでしょう。(参考:文化遺産オンライン「門松」)
仕事での新年の挨拶、いつまでが適切か

ビジネスシーンにおける新年の挨拶は、プライベートの場合よりも迅速かつ計画的に行うことが求められます。基本的な考え方は地域の慣習に倣いますが、どの地域であっても仕事始めの日から1月7日頃まで、遅くとも最初の営業週のうちに挨拶を済ませるのが、社会人としてのスマートなマナーと言えるでしょう。この期間が、気持ちを切り替えて業務に臨む姿勢を示す一つの目安となります。
仕事が本格的に稼働し始める中で、いつまでもお正月の挨拶を続けるのは、相手に「まだ正月気分が抜けていないのでは?」という、やや締まりのない印象を与えてしまう可能性があります。特に、社内の上司や同僚、部下に対しては、仕事始めの日の朝礼や始業時のタイミングで、簡潔かつ前向きな言葉で挨拶を済ませるのが理想的です。
取引先への挨拶回りや、年始に初めてお会いするお客様に対しては、松の内を少し過ぎた1月10日前後であれば「あけましておめでとうございます」と挨拶しても、決して失礼にはあたりません。ただし、1月中旬以降に初めて顔を合わせる場合には、後述するような「挨拶が遅れましたが」という一言を添えるか、別の表現に切り替えるのがおすすめです。
重要なのは、画一的なルールに固執するのではなく、相手との関係性や状況に合わせて柔軟に対応する判断力です。新年最初のコミュニケーションを円滑に進め、その後の業務をスムーズに開始するためにも、挨拶のタイミングは意識的にマネジメントしましょう。
新年の挨拶 ビジネスメールでの注意点

現代のビジネス環境では、年賀状に代わってメールで新年の挨拶を交わすケースが非常に増えています。手軽で迅速な反面、一斉送信などで事務的な印象を与えてしまうリスクもあります。相手に礼儀正しく、かつ好印象を与えるためには、いくつかの注意点をしっかりと押さえておく必要があります。
件名だけで要件が明確に伝わるようにする
年始の受信トレイは、多くの挨拶メールや通知で溢れかえっています。そのため、多忙な相手が一目で「誰から」「何のメールか」を判別できるように、件名を工夫することが極めて重要です。「新年のご挨拶【株式会社〇〇 営業部 鈴木太郎】」のように、用件に加えて会社名や氏名を明記しておくと、他のメールに埋もれることなく、開封してもらいやすくなります。
一斉送信(BCC)は極力避ける
BCC機能を使った一斉送信は、送信者にとっては効率的ですが、受信者側から見れば「大勢の中の一人」として扱われたと感じ、冷たい印象を与えてしまう可能性があります。特に重要な取引先や日頃からお世話になっている方へは、手間を惜しまず、宛名をきちんと記載して個別に送信するのが最も丁寧で、誠意が伝わる方法です。
お祝い事で避けるべき「忌み言葉」
お祝いのメッセージでは、縁起の悪い言葉や不吉な出来事を連想させる「忌み言葉」を避けるのが古くからのマナーです。「去年」の「去」は「離れる・去る」を連想させるため、「昨年」や「旧年」といった代替表現を用いるのが適切です。他にも、「失う」「枯れる」「倒れる」「衰える」なども避けるべき言葉です。
重複表現にも注意
よくある間違いとして「新年あけましておめでとうございます」という表現があります。これは「新年」と「年が明ける」で意味が重複しています。正しくは「あけましておめでとうございます」または「新年おめでとうございます」のどちらかを使いましょう。小さなことですが、言葉を正しく使う姿勢は、仕事の丁寧さにも繋がります。
これらの細やかなポイントを押さえるだけで、メールというデジタルのコミュニケーションであっても、相手への敬意と感謝の気持ちを十分に伝えることができます。丁寧な配慮が、新年のビジネス関係をより強固なものにしてくれるでしょう。
新年の挨拶が遅くなった場合のメール対応
多忙な年末年始を過ごす中で、うっかり挨拶が松の内を過ぎてしまったり、相手とのタイミングが合わずに挨拶が遅れたりすることは誰にでも起こり得ます。そのような場合でも、焦る必要はありません。状況に合わせた適切な言葉を選び、丁寧に対応することが大切です。
松の内(一般的には1月7日、地域によっては15日)を過ぎてしまった場合、「あけましておめでとうございます」という新年の賀詞(お祝いの言葉)の使用は控えるのがマナーです。その代わりに、以下のようなフレーズを用いて、本題に入ると非常にスムーズです。
挨拶が遅れた場合のクッション言葉フレーズ例
- 「新年のご挨拶が大変遅くなりましたが、本年もよろしくお願い申し上げます。」
- 「年始のご挨拶が遅れてしまい、誠に申し訳ございません。」
- 「松の内も過ぎてしまいましたが、本年も変わらぬご指導のほど、よろしくお願いいたします。」
さらに時期が遅れ、1月中旬から立春(例年2月4日頃)までの期間であれば、「寒中見舞い」として挨拶を送るのが最も丁寧で正式な方法となります。メールの場合、件名を「寒中お見舞い申し上げます」とし、「厳しい寒さが続いておりますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか」といった時候の挨拶から始め、その後に本年の厚誼をお願いする言葉を続けると自然な流れになります。
いずれの場合でも最も重要なのは、挨拶が遅れたことに対するお詫びの一言を誠実に添えることです。この一言があるかないかで、相手が受ける印象は大きく変わります。タイミングがずれてしまったという事実を正直に認め、丁寧に対応することで、かえって誠実な人柄が伝わり、良好な関係を維持することができるでしょう。
新年の挨拶遅れたメールに使える例文

実際に新年の挨拶が遅れてしまった際に使える、ビジネスメールの具体的な例文をご紹介します。こちらはあくまで基本的なテンプレートですので、相手との関係性や状況に合わせて、適宜言葉を補いながらご活用ください。
【件名】
新年のご挨拶【株式会社〇〇 鈴木太郎】
【本文】
株式会社△△
営業部 部長 山田様
いつも大変お世話になっております。
株式会社〇〇の鈴木です。
新年のご挨拶が遅れましたが、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
旧年中は、特に「〇〇プロジェクト」の件で格別のご厚情を賜り、心より感謝しております。
山田様のご支援なくして、あの成功はございませんでした。
本年も貴社のお役に立てるよう、一層のサービス向上を目指し誠心誠意努力する所存でございます。
貴社の益々のご発展を祈念しますとともに、本年も変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
(署名)
この例文の最大のポイントは、単に挨拶が遅れたことを詫びるだけでなく、「旧年中は、特に『〇〇プロジェクト』の件で~」というように、具体的なエピソードに触れている点です。テンプレート的な文章だけでなく、個人宛のメッセージであることが伝わる一文を加えることで、メール全体の価値が格段に上がります。
もし1月下旬以降にメールを送る場合は、件名を「寒中お見舞い申し上げます」とし、本文の冒頭を「厳しい寒さの折、山田様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。」のような時候の挨拶から始めると、より季節感に合った丁寧な文面になりますよ。
遅れてしまった時こそ、定型文で済ませずに、感謝の気持ちを具体的に伝える工夫をすることで、相手との信頼関係をより一層深める機会に変えることができます。
こちらの記事もオススメです(^^)/



新年の挨拶何時までかで変わる手土産選びのコツ
- 年始の挨拶にふさわしい手土産とは
- 目上用のギフトで失敗しないポイント
- 贈って喜ばれるおしゃれな手土産5選
- 自分へのご褒美におすすめの逸品
年始の挨拶にふさわしい手土産とは

年始の挨拶で相手先を訪問する際には、旧年中の感謝と新年の厚誼を願う気持ちを込めて、手土産を持参するのが丁寧で美しいマナーです。この時期に贈る手土産は特別に「お年賀(おねんが)」と呼ばれ、その起源は、新しい年の神様(年神様)の御前に人々がお供え物を持参したことに遡ると言われています。それゆえに、品物選びにもいくつかのポイントが存在します。
まず、現代において最も喜ばれ、かつ合理的なのは、お菓子や食品、消耗品といった、いわゆる「消え物」です。これらは相手に保管の負担や処分の手間をかけさせることがなく、ご家族や職場の皆さんで楽しんでもらえるため、手土産の王道として定着しています。選ぶ際の具体的なポイントは以下の通りです。
お年賀選びの4つの基本ポイント
- 日持ちするものを選ぶ:年始は来客が多く、贈り物が集中しがちです。相手が「すぐに消費しなければ」と焦らないように、少なくとも1週間以上の賞味期限があるものを選びましょう。
- 個包装になっているものを選ぶ:職場などで大勢に配る際、切り分ける手間が省け、また各自が好きなタイミングで手を汚さずに食べられるため、非常に喜ばれます。
- 常温で保存できるものを選ぶ:冷蔵や冷凍が必要な品は、相手の冷蔵庫のスペースを圧迫してしまう可能性があります。特に事前の確認がない限り、常温保存可能なものが親切です。
- 相手の人数を考慮に入れる:数が足りないのは最も避けたい事態です。訪問先の部署の人数や家族構成を事前に確認し、実際の人数よりも少し多めの数量が入ったものを用意すると安心感が生まれます。
私はいつも、定番のお菓子に加えて、その年に話題になったお店の品や、少し珍しいご当地のジュースなど、会話のきっかけになるようなアイテムをプラスすることがあります。相手の家族構成や好みが分かっている場合は、少し意外性のあるものを選ぶと「自分のために選んでくれた」という気持ちが伝わり、より喜ばれますよ。
最終的には、相手への感謝と思いやりの気持ちが最も大切です。その気持ちを形として表現するために、これらのポイントを参考に選んだ手土産は、きっと新年の挨拶をより温かく、心のこもったものにしてくれるでしょう。
目上用のギフトで失敗しないポイント

会社の上司や重要な取引先の重役、学生時代の恩師など、目上の方へ新年の挨拶に伺う際の手土産は、友人や同僚へのものとは一線を画し、特に慎重に選ぶ必要があります。ここで失敗しないためには、「品質の高さ」と「礼を尽くす格式」を両立させることが絶対的な鍵となります。
具体的には、以下のような点を総合的に判断して品物を選ぶと良いでしょう。
目上の方への手土産選びの心得
- 誰もが知る老舗や有名ブランドを選ぶ:品質が客観的に保証されており、ブランドの持つ信頼性が贈り主の敬意を代弁してくれます。奇をてらうよりも、王道を選ぶのが安全策です。
- パッケージが上品で高級感のあるものを選ぶ:中身の素晴らしさはもちろんですが、きちんと感のある落ち着いたデザインの包装も、相手への敬意を示す重要な要素です。
- 相手の好みや家族構成をリサーチする:お酒が好きな方には有名な酒蔵の限定酒、甘いものがお好きな方には高級和菓子店の季節の品など、事前に好みを把握しておけば、よりパーソナルな喜びを提供できます。
- 相場を意識する:安すぎるものは失礼にあたり、逆に高価すぎるものは相手に気を遣わせてしまいます。一般的に、3,000円~5,000円程度が適切な相場とされています。
そして、品物以上に重要とも言えるのが「のし紙」のマナーです。お年賀の場合、水引は「何度でも繰り返したいお祝い事」に用いる紅白の「蝶結び」を選びます。表書きは毛筆や筆ペンを使い、「御年賀」または「お年賀」と濃い墨で書くのが正式です。松の内を過ぎてから持参する場合は、表書きを「寒中御伺」と変更することを絶対に忘れないようにしましょう。(参考:高島屋「お年賀・冬ギフトのマナー」)
贈り物として避けるべき品物
現金や商品券は「生活の足しにしてください」という意味に取られかねず、目上の方には失礼とされています。また、「踏みつける」を連想させる履物(スリッパや靴下)や、「もっと勤勉に」という意味合いを持つ筆記用具なども避けるのが無難です。
品物選びから渡し方のマナーまで、細やかな配慮を積み重ねることで、相手への深い敬意と日頃の感謝の気持ちが、言葉以上に雄弁に伝わるはずです。
贈って喜ばれるおしゃれな手土産5選

せっかく贈るのであれば、定番の品も安心ですが、「センスが良いな」と相手の記憶に残るような、おしゃれな手土産を選びたいものです。ここでは、伝統を大切にしつつも現代的な感覚を取り入れた、贈る側も贈られる側も嬉しくなるような手土産のジャンルを5つ、具体的なイメージと共に深掘りしてご紹介します。
1. 人気パティスリーの芸術的な焼き菓子
普段は行列ができていてなかなか買えないような、話題のパティスリーが手掛ける限定クッキー缶やフィナンシェのアソートは、特別感の演出に最適です。味はもちろんのこと、宝石箱のように美しいデザインの缶や箱は、食べ終わった後も小物入れとして使ってもらえる付加価値があり、特に感度の高い女性やご家庭に喜ばれます。
2. 進化系「ネオ和菓子」
羊羹や最中といった伝統的な和菓子も、近年ではフルーツをふんだんに使ったフルーツ大福や、バターやチーズを組み合わせた進化系のどら焼き、カラフルでモダンなデザインの羊羹など、目にも新しいものが次々と登場しています。「ネオ和菓子」と呼ばれるこれらの品は、伝統の良さを知る年配の方から、新しいものを好む若い方まで、幅広い世代の心を掴む架け橋となるでしょう。
3. 食卓を豊かにするこだわりの調味料セット
料理好きな方や、健康志向、本物志向の方には、日常を少し豊かにしてくれる調味料セットが大変喜ばれます。例えば、全国各地の厳選素材から作られた高級なだしパックや、産地別の風味の違いが楽しめるオリーブオイルのミニボトルセット、木樽で熟成させたクラフト醤油などは、「自分ではなかなか買わないけれど、もらうと生活の質が上がる」アイテムの代表格です。
4. ストーリーのある専門店のコーヒーや紅茶
有名ロースタリーが焙煎したスペシャルティコーヒーのドリップバッグ詰め合わせや、世界的なコンテストで受賞歴のある高級紅茶ブランドのティーバッグセットは、誰にでも喜ばれる実用的なギフトです。単に味だけでなく、「〇〇という農園で丁寧に栽培された豆です」といったストーリーを伝えられる品を選ぶと、相手の知的好奇心も満たすことができ、より印象深い贈り物になります。
5. 華やかさを演出するプレミアムな飲み物
国産の希少な果物を贅沢に使った無添加のストレートジュースや、デザイン性の高いボトルが魅力のクラフトビール、入手困難な銘柄の日本酒なども、お祝いの席に華を添えるギフトとして大変人気です。お子様がいるご家庭にはジュースを、お酒好きな方にはその方の好みに合わせたお酒を選ぶといった、相手のライフスタイルを思いやった選択が喜ばれます。
これらのアイテムは、大手百貨店のバイヤーが厳選したギフトカタログや、感度の高いオンラインのセレクトショップなどで見つけることができます。また、InstagramなどのSNSで「#手土産」や「#お年賀ギフト」と検索すると、個性的でトレンド感のある贈り物を見つけるヒントが得られます。
自分へのご褒美におすすめの逸品

年始は、日頃お世話になっている方々へ感謝を伝える大切な機会ですが、それと同時に、新しい一年をエネルギッシュに駆け抜ける自分自身のために、少し特別な「ご褒美」を用意する絶好のタイミングでもあります。普段は少し躊躇してしまうような、質の良いものや心が豊かになる逸品を自分に贈ることで、気持ちを新たに素晴らしいスタートを切るのはいかがでしょうか。
ここでは、新年の幕開けにふさわしい、自分へのご褒美におすすめのジャンルを、具体的な体験価値と共にご紹介します。
一年の始まりに「これを糧に、また一年頑張ろう!」と心から思えるような特別なものがあると、日々のモチベーションが驚くほど変わりますよね。私が自分へのご褒美に選ぶなら、滅多に手が出ない老舗ホテルのシグネチャーチョコレートや、専門店のチーズプロフェッショナルが選んだ、とっておきのチーズプラトーです。
心と体を満たす自分へのご褒美アイデア
- 高級ホテルの珠玉のスイーツ:普段はショーケースを眺めるだけの一流ホテルのパティスリーが創り出す、芸術品のようなケーキやボンボンショコラ。その一口は、日常の喧騒を忘れさせてくれる至福の体験をもたらします。
- 産地直送の贅沢お取り寄せグルメ:全国の美食を自宅で心ゆくまで楽しめるお取り寄せ。A5ランクのブランド牛ですき焼きを楽しんだり、北海道から届く新鮮な海の幸に舌鼓を打ったり、食を通して旅気分を味わうのも格別です。
- 物語を味わう希少な日本酒やワイン:自分の好きな銘柄の限定醸造品や、信頼するソムリエがおすすめするバックヴィンテージの一本。そのお酒が辿ってきた歴史や造り手の想いに心を馳せながら、じっくりと味わう時間は、大人ならではの知的な楽しみです。
- 五感を癒すリラックスバスグッズ:天然エッセンシャルオイルが豊かに香るバスオイルや、上質なハーブを使った入浴剤、肌触りの良いバスローブなど。日々の疲れをリセットし、心と体を深く癒すためのセルフケアアイテムへの投資は、未来の自分への最高の贈り物です。
新しい年の始まりという節目に、まず自分自身を大切にし、労う時間を持つことは、一年を通してポジティブで健やかなマインドを維持するための重要なエネルギー源となります。ぜひ、あなただけのとっておきの逸品を見つけ、輝かしい一年のスタートを切ってください。
新年の挨拶何時までか確認し準備しよう
- 新年の挨拶は一般的に「松の内」までに行う
- 松の内は関東では1月7日、関西では1月15日が目安
- どちらか迷った場合は短い方の1月7日を基準にすると無難
- ビジネスシーンでは仕事始めから初週のうちに挨拶を済ませるのが理想
- 松の内を過ぎた場合は「あけましておめでとうございます」は使わない
- 挨拶が遅れた際は「新年のご挨拶が遅れましたが」と一言添える
- さらに遅れた場合は「寒中見舞い」として挨拶する
- ビジネスメールでは件名を分かりやすくし一斉送信は避ける
- 「去年」は忌み言葉なので「昨年」「旧年」を使う
- 年始の挨拶で持参する手土産は「お年賀」と呼ぶ
- 手土産は日持ちする個包装の「消え物」が喜ばれる
- 目上の方への手土産は品質と格式を重視し老舗や有名ブランドを選ぶ
- お年賀には紅白蝶結びののし紙をかけ表書きは「御年賀」とする
- おしゃれな手土産は人気店のスイーツやこだわりの調味料などがおすすめ
- 新しい一年を頑張る自分へのご褒美を用意するのも素敵
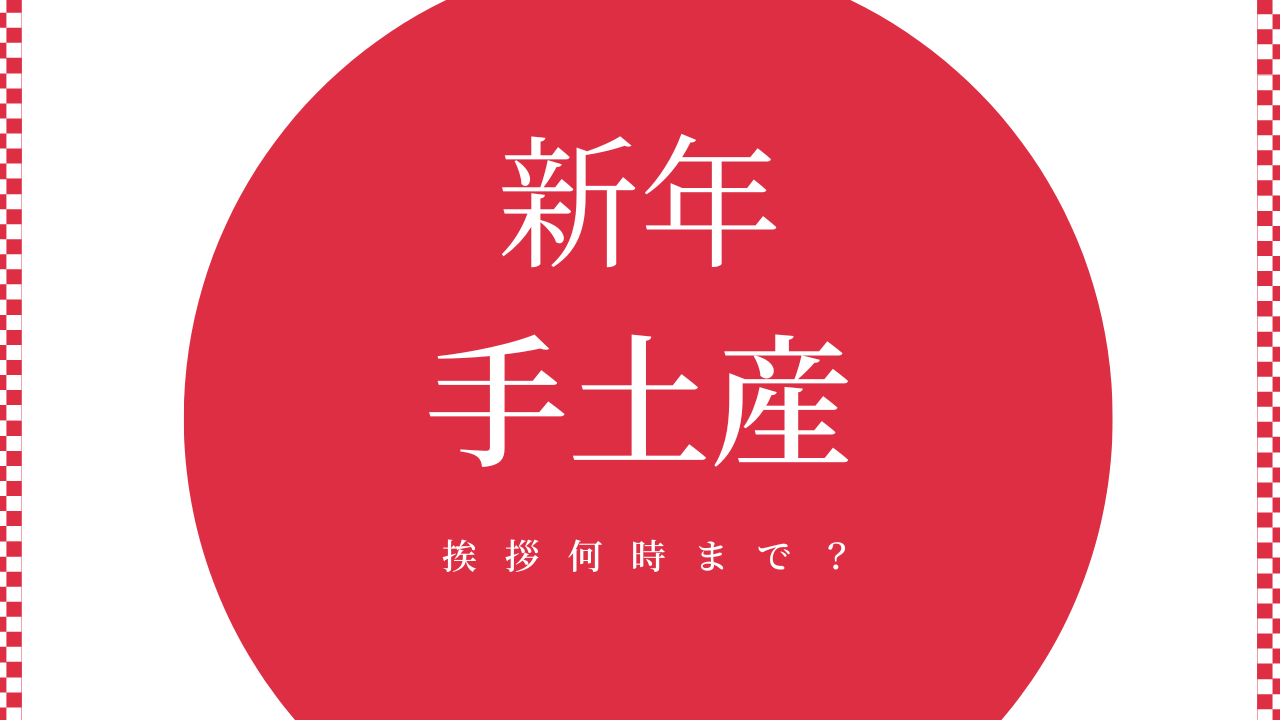


コメント