【お中元は何時まで?】地域別の時期と遅れた時のマナー解説
日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝える、日本の美しい習慣「お中元」。いざ贈ろうと考えた時、「一体いつまでに贈れば失礼にならないのだろう?」と、その時期について迷われた経験はありませんか。特に、上司や遠方の親戚など、マナーが気になる相手であればなおさらです。関東と関西で時期が違うという話は有名ですが、具体的にどう違うのか、そして6月中に贈るのは早すぎるのか、もしお中元の時期を過ぎたらどうすれば良いのか、疑問は尽きません。
この記事では、そんなお中元の時期に関するあらゆる疑問に専門的な視点からお答えします。地域ごとの正しい期間から、知っておくべき相場や贈り方のマナー、贈って喜ばれるおすすめの品、そして万が一遅れてしまった場合のスマートな対処法まで、必要な情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、自信を持って心のこもったお中元を贈れるようになるでしょう。
- 地域ごとのお中元の正しい時期がわかる
- 時期を過ぎた場合の失礼のない対応方法
- お中元の相場や基本的なマナー
- 贈って喜ばれるおすすめのギフト
お中元は何時まで?地域別の基本時期
- お中元はいつまで贈っても大丈夫ですか?
- 関東と関西のお中元の時期の違い
- 6月にお中元を贈るのは早い?
- お中元の相場と基本的なマナー
- 迷ったらこれ!おすすめのお中元ギフト
お中元はいつまで贈っても大丈夫ですか?

お中元を贈る上で最も大切な原則は、「贈る相手が住んでいる地域の慣習に合わせる」ということです。この贈り物は、日本全国で一律の期間が定められているわけではなく、それぞれの地域で古くから受け継がれてきた文化や歴史的背景によって、贈るべき最適なタイミングが異なります。
では、なぜこれほどまでに地域差が生まれたのでしょうか。その根源は、お中元の由来とも深く関わる「お盆」の時期にあります。お中元は、もともと中国の道教の習わしが起源とされ、日本ではお盆の時期に親族や近隣の人が贈り物を持ち寄る習慣と結びつきました。そして、明治5年(1872年)の改暦で新暦(グレゴリオ暦)が採用された際、お盆の行事を新暦の7月15日を中心に行う地域(新暦盆)と、旧暦に近い8月15日を中心に行う地域(月遅れ盆)に分かれました。このお盆の時期の違いが、そのまま現在のお中元の時期の違いとして定着したのです。
そのため、「お中元は7月中旬まで」という認識だけで贈ってしまうと、相手の地域によっては時期外れとなり、意図せず失礼にあたる可能性があります。ビジネスシーンや親戚付き合いなど、相手への配慮が特に求められる場面では、事前に相手の居住地の慣習を確認する一手間が、より深い感謝の気持ちを伝えることに繋がります。
ポイント
お中元を贈る時期の基本は、全国一律ではなく相手の居住地域の慣習に合わせることです。もし不明な場合は、少し早めに手配を開始し、相手の地域について調べてみることをお勧めします。
関東と関西のお中元の時期の違い

お中元の時期における地域差の最も代表的な例が、関東地方と関西地方です。この二つのエリアの違いを正確に理解しておくことが、贈り間違いを防ぐための重要な鍵となります。
具体的には、前述の通り新暦盆を採用した地域が多い関東では、7月1日~7月15日という比較的短い期間がお中元シーズンです。一方、旧盆(月遅れ盆)の慣習が今も色濃く残る関西では、7月15日~8月15日の約1ヶ月間が一般的とされ、ゆとりを持った期間設定になっています。
このパターンは関東・関西だけでなく、他の多くの地域にも当てはまります。例えば、東北地方は関東式に、中国・四国地方は関西式に準じることが多いです。しかし、中には独自の慣習を持つ地域も存在します。より安心して贈れるよう、詳細な地域別の時期を以下の表にまとめました。
【2025年版】地域別お中元の時期一覧
| 地域 | 一般的な時期 | 備考・詳細 |
|---|---|---|
| 北海道 | 7月15日~8月15日 | 基本的には関西式ですが、物流の発達やビジネス習慣の変化から、関東式に合わせて7月上旬に贈るケースも増えています。 |
| 東北・関東 | 7月1日~7月15日 | 期間が約2週間と短いため、特に人気商品は早めの準備が不可欠です。6月下旬から配送予約をするのが賢明です。 |
| 北陸 | 地域により混在 | 例えば石川県では、金沢市など都市部は関東式、能登地方は関西式と、同じ県内でも文化圏によって時期が異なります。 |
| 東海・関西・中国・四国 | 7月15日~8月15日 | 月遅れ盆の慣習が根強いエリアです。ただし、ビジネスシーンでは関東式に合わせる企業も見られます。 |
| 九州 | 8月1日~8月15日 | 全国で最も時期が遅いのが特徴です。お盆の帰省シーズンと重なるため、相手の在宅状況に配慮が必要です。 |
| 沖縄 | 旧暦の7月13日~15日 | 旧暦に沿うため、毎年日付が大きく変動します。2025年の沖縄の旧盆は新暦の8月8日~8月10日の3日間です。(参照:沖縄観光情報WEBサイト 沖縄物語) |
注意点
北陸地方のように判断が難しい地域の方へ贈る場合や、相手の正確な住所や慣習が不明な場合は、全国的に見ても贈り始めの時期として受け入れられやすい7月15日前後に品物が届くように手配するのが最も無難な選択と言えるでしょう。
6月にお中元を贈るのは早い?

「6月にお中元を贈るのは、さすがに早すぎるのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、結論として、現代においては6月下旬から贈り始めることは一般化しており、マナー違反とは見なされないケースがほとんどです。
この背景には、社会の変化が大きく影響しています。主要な理由としては、以下の2点が挙げられます。
- ギフト商戦の早期化:三越伊勢丹などの大手百貨店や主要なオンラインショップでは、6月上旬、早いところでは5月下旬からお中元ギフトの特設ページを開設し、早期割引などのキャンペーンを展開します。これにより、贈る側も受け取る側も「お中元は6月から始まる」という意識が浸透しつつあります。
- 配送の集中回避:特に関東の7月上旬は、全国からのお中元が集中し、物流に大きな負荷がかかります。希望の日時に届けられない、配送が遅延するといったリスクを避けるため、贈る側が意図的に時期をずらすという実用的な理由も大きいのです。
ただ、現在の私は、この新しい潮流が全ての人に受け入れられているわけではない点も指摘しておきたいと思います。特に、古くからの慣習を大切にされているご年配の方や、格式を重んじる間柄の方へ贈る際には、「少しせっかちな印象を与えてしまう」可能性もゼロではありません。相手の価値観や関係性を考慮し、心配な場合はやはり伝統的な期間である7月1日を過ぎてから届くように手配するのが最も丁寧な対応です。
個人的には、人気のある限定品を確実に手に入れたい場合や、相手にゆっくり品物を選んでもらいたい場合は、6月中に「今年のお中元はこちらの品をお贈りしますね」と一報入れておくのもスマートな方法だと思います。
お中元の相場と基本的なマナー

感謝の気持ちを形にするお中元ですが、その気持ちを正しく伝えるためには、相手に余計な気を遣わせないための相場感と、失礼にあたらないための基本的なマナーの知識が不可欠です。
お中元の相場について
お中元にかける金額は、相手との関係の深さや日頃のお付き合いの度合いによって調整するのが一般的です。市場調査などを見ても、平均的には3,000円~5,000円がボリュームゾーンとなっています。これは、相手がお返し(返礼)を考える際に過度な負担にならず、かつ贈る側の感謝の気持ちもしっかりと伝わる、絶妙なバランスの価格帯だからです。
- 両親や兄弟、親しい友人など:3,000円程度
- お世話になった上司や取引先、仲人など:5,000円程度
- 特に重要な取引先や、格別にお世話になった方:5,000円~10,000円程度
一度贈ったら、翌年以降も同程度の金額の品物を選び続けるのが暗黙のルールです。年によって金額が大きく上下すると、相手を困惑させてしまう可能性があるため注意しましょう。もし関係性の変化などでお中元自体をやめたい場合は、後述する「やめどき」の項を参考にしてください。
基本的なマナー
心を込めて選んだ品物も、贈り方のマナーが伴っていなければ、その価値は半減してしまいます。以下の点は必ず押さえておきましょう。
- のし紙:品物には必ず「のし紙」をかけます。水引は、「紅白の蝶結び(花結び)」を選びましょう。蝶結びは、何度でも結び直せることから、「何度あっても嬉しいこと」に使われる縁起の良いものです。
- 表書き:水引の上段中央に、毛筆や筆ペンで「御中元」と濃くはっきりと書きます。
- 名入れ:水引の下段中央に、表書きよりも少し小さな字で、贈り主のフルネームまたは姓を書きます。
喪中の場合のマナー
お中元はお祝い事ではなく、日頃の感謝を伝える季節の挨拶ですので、自分や相手が喪中(故人が亡くなってから一年以内)であっても、贈ること自体はマナー違反ではありません。ただし、故人が亡くなってから四十九日法要が終わるまでの「忌中」の期間は、ご遺族も心身ともに落ち着かない時期ですので、贈るのは避けるのが賢明です。その場合は、時期をずらして「暑中見舞い」や「残暑見舞い」として贈るのが最も丁寧な対応です。また、喪中の相手に贈る際は、お祝いを連想させる紅白の水引が印刷されたのし紙は避け、無地の奉書紙や白い短冊に表書きをするのが望ましいとされています。
迷ったらこれ!おすすめのお中元ギフト

毎年のお中元選びは、楽しい反面、悩ましいものでもあります。もし品物選びに迷ったら、「季節感」「日持ち」「家族構成」の3つのキーワードを軸に選ぶと、失敗が少なくなります。夏にぴったりの涼やかなものや、家族みんなで分け合えるものは、どのような相手にも喜ばれやすいでしょう。
ここでは、定番でありながらも確実に喜ばれる、おすすめのギフトジャンルをその理由とともにご紹介します。
- 涼やかなスイーツ類:フルーツをふんだんに使ったゼリーや、老舗の和菓子店の水ようかん、有名パティスリーのアイスクリームなどは、夏のギフトの王道です。見た目も華やかで、暑い季節に涼を届けてくれます。個包装になっているタイプは、オフィスへの贈り物としても重宝されます。
- こだわりのドリンク類:果汁100%のプレミアムジュースや、有名店の瓶入りアイスコーヒー、クラフトビール(地ビール)の飲み比べセットなども人気が高いです。お子さんがいるご家庭にはジュース、お酒が好きな方にはビールなど、相手のライフスタイルに合わせて選べるのが魅力です。
- 夏の定番・麺類:そうめんやひやむぎ、稲庭うどんなどの高級感のある乾麺は、日持ちがするため、受け取った側も自分のペースで消費できるというメリットがあります。食欲が落ちがちな夏でもつるっと食べられるため、実用的なギフトとして根強い人気を誇ります。
- 少し贅沢なグルメ:国産うなぎの蒲焼や、ブランドハム・ソーセージの詰め合わせ、旬のフルーツなども定番です。普段はなかなか自分では買わないような「ちょっと贅沢」なグルメは、食卓を豊かにし、特別感を演出してくれます。
避けた方が良い品物
感謝を伝える贈り物として、縁起が悪いとされる品物は避けるのが無難です。「踏みつける」を連想させる履物(スリッパや靴下など)や、「縁を切る」を連想させる刃物(包丁やハサミなど)は、お中元にはふさわしくないとされています。
結局のところ、一番大切なのは「相手のことをどれだけ考えられたか」という点に尽きます。相手の好みはもちろん、家族構成や健康への配慮(減塩や糖質オフなど)、アレルギーの有無までリサーチして選んだ一品は、きっと相手の心に響くはずです。
こちらの記事もオススメです(^^)/
お中元は何時まで?遅れた時の対処法
- お中元の時期を過ぎたらどうする?
- お中元が遅れた場合どうなりますか?
- お中元が遅れた場合ののしは?
- お中元のやめどきはいつですか?
- 参考情報:お歳暮はいつ贈る?
お中元の時期を過ぎたらどうする?

多忙な日々の中で、「しまった、お中元の時期をうっかり過ぎてしまった!」という事態は誰にでも起こり得ます。しかし、そんな時でも決して諦める必要はありません。日本の贈答文化には、こうした状況をスマートに乗り切るための素晴らしい知恵があります。
前述の通り、まずはお贈りする相手の地域のお中元期間を正確に再確認してください。その上で、もし期間を過ぎてしまっていた場合は、贈り物の名目を季節の挨拶へと切り替えて対応します。具体的には、以下の二段階の対応となります。
- お中元の時期を過ぎてから、暦の上で秋が始まる「立秋」の前日までは「暑中見舞い(しょちゅうみまい)」として贈ります。
- 立秋を過ぎてから、おおむね8月末頃までは「残暑見舞い(ざんしょみまい)」として贈ります。
「暑中見舞い」や「残暑見舞い」は、もともと夏の最も暑い時期に相手の健康を気遣い、自身の近況を伝える挨拶状の文化です。ここに品物を添えることで、時期外れのお中元ではなく、「厳しい夏を健やかにお過ごしください」という心のこもった季節の贈り物として、自然に受け取ってもらえます。お中元用に準備していた品物をそのまま贈って構いませんので、時期に合った正しい「のし紙」にだけ変更しましょう。
こちらの記事もオススメです(^^)/

お中元が遅れた場合どうなりますか?

もし、お中元の時期を過ぎているにもかかわらず、のし紙の表書きを「御中元」のまま贈ってしまったらどうなるのでしょうか。これは、結論から言うと明確なマナー違反と見なされてしまう可能性が高いです。
日本の贈答文化は、季節感を非常に大切にします。季節外れの表書きは、相手に対して「時期や慣習に配慮ができない人」という、不本意な印象を与えかねません。特に、ビジネス上の関係者や礼儀を重んじる目上の方に対しては、感謝を伝えるどころか、かえって心証を損ねてしまうリスクも伴います。
お中元が遅れてしまった場合は、必ず季節の挨拶である「暑中見舞い」や「残暑見舞い」に切り替える、というルールを徹底することが、信頼関係を維持する上で非常に重要です。その際、ひと手間加えることで、遅れてしまったことを誠実にカバーできます。
遅れた時の一言メッセージ文例
品物に短い手紙やメッセージカードを添えるだけで、印象は大きく変わります。
「猛暑の折、〇〇様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、本来であればお中元の時期にご挨拶申し上げるべきところ、大変遅くなり誠に申し訳ございません。心ばかりの品ではございますが、どうぞご笑納ください。」
注意:9月以降の対応
8月中に「残暑見舞い」として贈ることができなかった場合、9月以降に夏の挨拶として贈るのは季節外れとなります。その場合は潔くその年の夏のご挨拶は見送り、年末の「お歳暮」で、一年間の感謝を込めてより丁寧にご挨拶するのが最善の策です。
お中元が遅れた場合ののしは?

お中元の時期を過ぎてしまった際に、最も重要な手続きが「のし紙」の表書きを正しく変更することです。時期に応じた適切な表書きを選ぶことが、マナーを守る上での最大のポイントになります。その切り替えの基準となるのが、二十四節気の一つである「立秋(りっしゅう)」です。
時期に応じた「のし」の表書きルール
- お中元の時期を過ぎてから立秋の前日まで
→ 表書きは「暑中御見舞」とします。
- 立秋の日以降から8月末まで
→ 表書きは「残暑御見舞」とします。
使用する水引は、お中元と同様に「紅白の蝶結び」が印刷されたもので問題ありません。
豆知識:2025年の立秋はいつ?
「立秋」は暦の上で秋が始まる日とされ、この日を境に夏の挨拶が「暑中」から「残暑」へと変わります。国立天文台の暦計算室によると、2025年の立秋は8月7日です。この日を基準に表書きを使い分けましょう。
より丁寧に対応するなら「御伺」を使おう
ここで、もう一歩進んだマナーをご紹介します。「見舞う(みまう)」という言葉には、相手を訪ねたり、慰めたりするという意味合いがあり、本来は同等か目下の人に対して使う言葉とされています。そのため、贈る相手が恩師、上司、重要な取引先といった目上の方の場合は、表書きを以下のように変えることで、より深い敬意を示すことができます。
- 暑中見舞いの場合 → 「暑中御伺(しょちゅうおうかがい)」
- 残暑見舞いの場合 → 「残暑御伺(ざんしょおうかがい)」
「伺う(うかがう)」という謙譲語を使うことで、「ご機嫌はいかがでしょうかとお伺いします」という、へりくだった丁寧なニュアンスになります。相手との関係性に応じて使い分けることで、きめ細やかな配慮が伝わるでしょう。
お中元のやめどきはいつですか?

一度始めると、どのタイミングでやめるべきか悩みがちなのがお中元の習慣です。「お中元のやめどき」は、多くの方が一度は考えるテーマかもしれません。
大前提として、お中元は義務ではありません。しかし、日本のコミュニケーション文化においては、一度贈答関係が始まった相手に対し、明確な理由なく一方的にやめてしまうのは、相手に「何か気に障ることをしてしまっただろうか」といった無用な心配をかけてしまう行為と見なされがちです。そのため、一般的には一度始めたら最低でも3年間は贈り続けるのが、相手との良好な関係を保つ上での一つの目安とされています。
その上で、お中元をやめることを検討しても良い自然なタイミングとしては、以下のようなライフステージの変化が挙げられます。
- 相手との関係性の変化:お世話になった上司が定年退職された、転勤や引っ越しで疎遠になった、仲人のお役目を終えたなど、お付き合いの区切りがついた時。
- 自分自身の状況の変化:定年退職や転職で経済状況が変わった、高齢になり品物選びや手配が身体的な負担になってきた時。
いずれの理由であっても、最も大切なのは「突然やめない」ということです。最後の贈り物となるお歳暮などに手紙を添え、「長年にわたり大変お世話になりました。今後のご厚情につきましては、どうぞご放念ください」といった形で、感謝の言葉と共に今後の辞退の意向を丁寧に伝えるのが、最も美しい終わり方です。相手への感謝と配慮を忘れずに、円満な関係を維持しましょう。
こちらの記事もオススメです(^^)/
参考情報:お歳暮はいつ贈る?

お中元と対になる年末の贈り物、それが「お歳暮」です。お中元が「半年間の感謝」を伝える夏の挨拶であるのに対し、お歳暮は「一年間の感謝」を伝える、より総括的な意味合いを持つ重要な挨拶と位置づけられています。
お歳暮を贈る時期にも若干の地域差はありますが、全国的に見ると12月上旬から12月20日頃までに相手の手元に届くように手配するのが最も一般的で丁寧なマナーです。年の瀬で誰もが慌ただしくなる12月下旬、特に仕事納め以降の年末ギリギリに届くのは、相手の迷惑になる可能性があるため避けるのが賢明です。
もし、お歳暮の時期にも間に合わなかった場合は、松の内(元旦から1月7日、または15日)までは「御年賀(おねんが)」、それ以降立春(2月4日頃)までは「寒中御見舞(かんちゅうおみまい)」として贈ることができます。
もしお中元を贈りそびれてしまった場合は、その分お歳暮で一年間の感謝をしっかり伝えるという考え方もあります。お中元とお歳暮の両方を贈るのが最も丁寧ですが、どちらか一方にする場合は、一年の締めくくりであるお歳暮を優先するのが一般的と覚えておくと良いでしょう。
まとめ:お中元は何時までか確認を
お中元は、単なる季節の贈り物ではなく、相手への感謝と健康を気遣う気持ちを伝える日本の大切なコミュニケーション文化です。この記事で解説したポイントを押さえ、自信を持って心からの贈り物をしましょう。最後に、重要な点をリストで振り返ります。
- お中元を贈る時期は全国一律ではない
- 贈る相手が住んでいる地域の慣習に合わせるのが基本マナー
- 関東地方は7月1日から7月15日が目安
- 関西地方は7月15日から8月15日が目安
- 九州は8月1日から15日、沖縄は旧盆の3日間
- 判断に迷ったら7月15日頃に届くように手配するのが無難
- 最近は配送の集中を避けるため6月下旬から贈る人も増えている
- お中元の相場は3,000円から5,000円が一般的
- のし紙は「紅白の蝶結び」で表書きは「御中元」
- 時期を過ぎてしまったら「暑中見舞い」として贈る
- 立秋(2025年は8月7日)を過ぎたら「残暑見舞い」として贈る
- のしの表書きは時期に合わせて必ず変更する
- 目上の方には「御伺」を使うとより丁寧
- 9月以降に贈るのは季節外れになるため避ける
- お中元をやめる際は突然ではなく丁寧に伝えることが大切
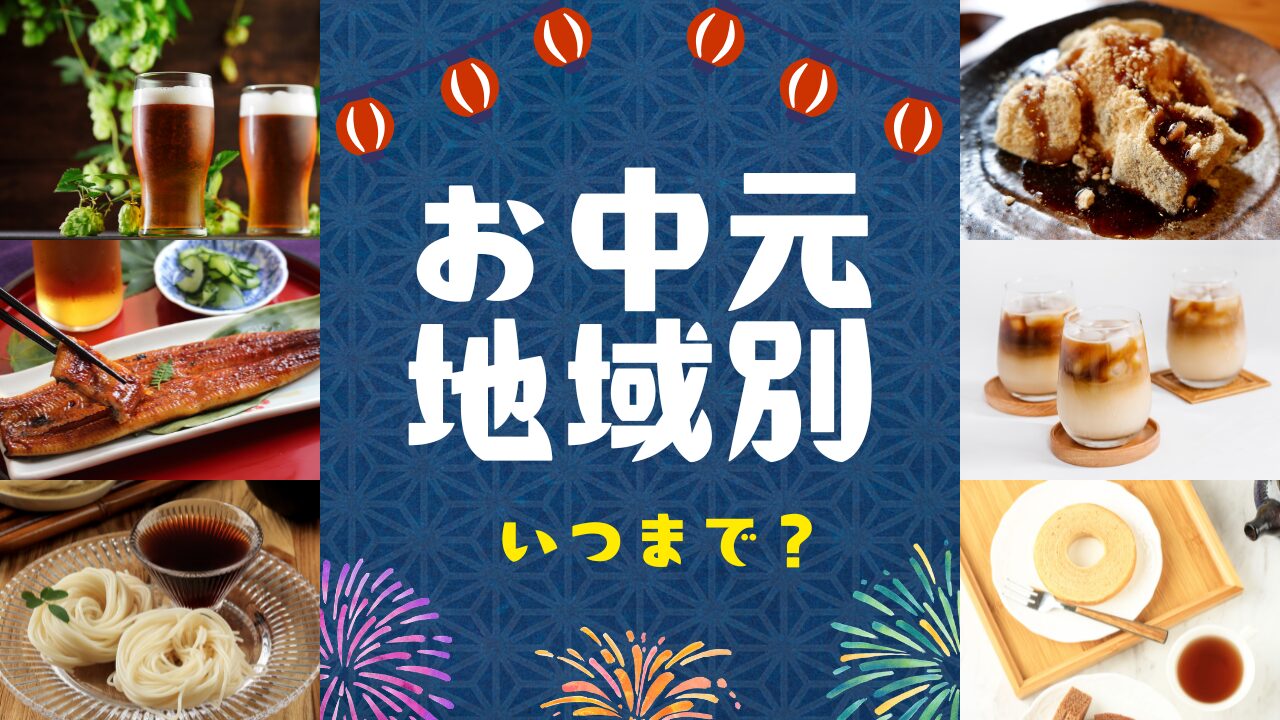


コメント