結婚する娘に持せる物リスト|令和の嫁入り道具と親の準備
大切に育ててきた娘さんの結婚が決まり、喜びもひとしおのことと思います。しかし、同時に「結婚する 娘に持せる物はいったい何が良いのだろう?」と、頭を悩ませていらっしゃるのではないでしょうか。嫁入り道具 現在のスタイルは昔と大きく異なり、嫁入り道具令和の考え方では、より実用的な品が選ばれる傾向にあります。例えば、結婚する娘に持せる お金の問題や、嫁入り道具 結納金なしの場合はどうするべきかなど、考えるべきことは少なくありません。結婚 母から娘へ プレゼントとして、結婚する娘に持せる着物や結婚する娘に持せる 数珠といった伝統的な品も素敵ですが、愛情を込めた結婚する娘に 手作り プレゼントを選ぶ方も増えています。
この記事では、現代の結婚スタイルに合わせた娘さんへの贈りもの選びを、具体的な品物や相場を交えて分かりやすく解説します。
- 現代における「嫁入り道具」の考え方
- 娘に贈ると喜ばれる具体的な品物と金額の相場
- 伝統的な品々に込められた親の想い
- 後悔しない贈りものを選ぶためのポイント
結婚する娘に持せる物としての嫁入り道具
- 嫁入り道具:現在のトレンドとは
- 嫁入り道具令和のスタイルを紹介
- 比較としての伝統的な嫁入り道具は?
- 嫁入り道具結納金なしの場合の考え方
嫁入り道具:現在のトレンドとは

現代における「嫁入り道具」は、かつてのように家の格式を示すための豪華絢爛な品々ではなく、娘さん夫婦の新しい生活を具体的に、そして豊かにするための実用的なアイテムが中心となっています。この変化の背景には、女性の社会進出やライフスタイルの多様化、そして核家族化が進んだ現代の住宅事情が大きく影響しています。
例えば、収納が充実したマンションやアパートに住むカップルにとって、大きな桐たんすは場所を取るだけの荷物になりかねません。それよりも、日々の家事を助けてくれる最新の家電や、二人の時間を快適にするインテリアの方がはるかに喜ばれるのです。
生活必需品としての家電や家具
現在のトレンドとして最も人気が高いのは、冷蔵庫、ドラム式洗濯乾燥機、エアコン、ロボット掃除機といった大型家電です。これらは生活に不可欠でありながら高価なため、親からの最も現実的な援助として贈られるケースが多く見られます。特に、共働きが増えた現代においては、家事の負担を軽減する「時短家電」の需要が非常に高まっています。
将来の家族構成の変化を見越して少し大きめのファミリーサイズの冷蔵庫を選んだり、洗濯から乾燥までを一台でこなせる洗濯乾燥機を贈ったりすることで、長く二人の生活を支えることができます。
また、家具であれば、新居の雰囲気に合わせたダイニングテーブルセットや、リラックスできるソファなどが選ばれます。ここでの最も重要なポイントは、必ず事前に娘さん本人やパートナーとよく相談し、彼らの好みや部屋のサイズ、生活動線に合うものを選ぶことです。サプライズも素敵ですが、大きな買い物で失敗しないためには、本人たちの意思を最大限に尊重する姿勢が求められます。
現在の嫁入り道具選びの3つのポイント
- 実用性重視: 見栄えよりも、新生活ですぐに使えるものが基本。
- 時短・高機能家電: 共働き夫婦の生活をサポートする質の良い家電が人気。
- 本人たちとの対話: 新居のインテリアや本人の好みを尊重することが何よりも大切。
言ってしまえば、昔の「家」と「家」の結びつきのために準備された道具から、「夫婦」二人の新しい生活を快適にスタートさせるための道具へと、その本質的な意味合いが大きく変化しているのです。
嫁入り道具令和のスタイルを紹介

「令和」の嫁入り道具は、現在の実用性重視のトレンドをさらに一歩進め、よりパーソナルで、無駄を削ぎ落とした合理的な考え方に基づいています。そのキーワードは「ミニマム」「シェア(分担)」、そして親から子への「想いの継承」です。
かつてのように「嫁入り道具一式」というパッケージで揃えるのではなく、新郎新婦が本当に必要なものだけをリストアップし、それに応じて親がサポートするというスタイルが主流です。どちらかが一人暮らしで使っていた愛着のある家具や家電を、そのまま新生活で活用するケースも全く珍しくありません。
厳選された質の良い「暮らしを豊かにする」もの
令和のスタイルでは、品数は少なくても、一つひとつが質の良いもの、デザイン性が高く長く愛用できるものを贈る傾向が強まっています。例えば、毎日の料理が楽しくなるような高性能な調理家電(電気圧力鍋やスチームオーブンレンジなど)や、少し高級なブランドの食器、肌触りの良い上質なリネン類などが挙げられます。
これらは単なる「モノ」ではなく、日々の生活の質を向上させ、二人の暮らしを豊かに彩るアイテムです。そして、それを使うたびに親の愛情や応援の気持ちを感じられる、特別な品となるでしょう。
最近では、新郎新婦が共同で使うものとして、どちらの親が何を贈るか、事前にリストを見ながら話し合って分担するケースも増えています。例えば「家電は新婦側で、家具は新郎側で」といったように、片方の家に負担が偏らないように配慮する。これも令和らしいスマートで思いやりのあるスタイルと言えるかもしれませんね。
最も合理的で喜ばれる「現金」という選択肢
もう一つの大きな特徴は、現金や各種ギフトカード、商品券を贈るケースが非常に増えていることです。これは、「自分たちの好きなものを、本当に必要なタイミングで揃えてほしい」という親心からくる、非常に合理的で現代的な選択と言えます。品物選びに自信がない場合や、娘夫婦のこだわりが強い場合にも最適な方法です。
新郎新婦にとっても、自分たちのセンスでインテリアを統一したり、最新の家電を比較検討して選んだりできるため、満足度が非常に高い贈り物として大変喜ばれます。
比較としての伝統的な嫁入り道具は?

現代の合理的なスタイルを深く理解するためには、かつての伝統的な嫁入り道具がどのようなものであったかを知ることが役立ちます。これらは単なる家財道具という枠を超え、嫁ぐ娘への親の愛情の深さや、実家の経済力、そして家の格式を示す非常に重要な象徴でもありました。
その品々は、花嫁が嫁ぎ先で生活に困ることなく、また、お客様をもてなす際にも恥ずかしくないように、という親の切なる願いを込めて、丹念に準備されたものです。
| カテゴリー | 伝統的な嫁入り道具(一例) | 現代の嫁入り道具(一例) |
|---|---|---|
| 家具 | 桐たんす、鏡台(三面鏡)、和箪笥、整理箪笥 着物や衣類を湿気から守り、嫁ぎ先での生活の基盤となるもの。 |
ダイニングテーブル、ソファ、ベッド、テレビボード 夫婦二人の生活空間を快適にするためのインテリア。 |
| 家電 | (当時はなし) | 冷蔵庫、洗濯乾燥機、エアコン、調理家電 日々の家事を効率化し、生活を豊かにするもの。 |
| 寝具 | 豪華な刺繍入りの婚礼布団、来客用の布団・座布団一式 夫婦の健康と、お客様へのおもてなしを象徴するもの。 |
夫婦二人分の質の良いベッドマットレスや羽毛布団 日々の睡眠の質を高めるためのパーソナルなもの。 |
| 衣類 | 黒留袖、喪服(和装)、訪問着などの着物一式 冠婚葬祭や公式な場で家の顔として恥ずかしくないためのもの。 |
フォーマルウェア(洋装)、喪服(洋装) 現代の社会生活で必要となる、実用的な冠婚葬祭用の衣服。 |
| その他 | 漆器の食器一式、裁縫道具、長持(衣類運搬用の箱) 家事全般を滞りなく行うための道具。 |
パールジュエリー、印鑑、現金、商品券 個人の財産や、社会的な信用を証明するもの。 |
この表を見ると、伝統的な嫁入り道具が「家」という共同体の中での生活や、対外的な格式を強く意識していたのに対し、現代では夫婦二人の「新しい生活」そのものを快適にし、楽しむことを重視しているという価値観の変化が明確に見て取れます。
豆知識:嫁入りトラック
かつて名古屋などの一部地域では、嫁入り道具を荷台がガラス張りになった特別なトラックに乗せ、紅白の幕で華やかに飾り付けて町内を走りながら嫁ぎ先まで運ぶ「嫁入りトラック」という文化がありました。これは、娘の幸せな門出を近隣に披露し、祝福を分かち合うという意味合いがあったそうです。この風習からも、嫁入り道具がいかに重要なイベントであったかがうかがえます。
もちろん、だからといって伝統的な品々に込められた「娘の幸せを願う親心」が失われたわけではありません。むしろ、その想いは形を変え、パールや印鑑といった現代的な贈り物の中に、今もなお大切に受け継がれています。
嫁入り道具や結納金なしの場合の考え方

かつて嫁入り道具は、結婚の約束を正式に交わす儀式である「結納」の際に、男性側から女性側へ贈られる「結納金」を使って準備するのが一般的でした。しかし、ゼクシィ結婚トレンド調査2023によると、結納を行ったカップルは全体のわずか7.9%に留まり、現在では結納自体を行わないスタイルが主流となっています。そのため、「結納金なし」の場合に嫁入り道具をどう準備すれば良いのかは、多くのご家庭が直面する課題です。
最も重要なのは両家でのコミュニケーション
結論から言えば、結納金の有無にかかわらず、嫁入り道具や新生活の準備に関する費用負担に決まったルールはありません。最も大切なのは、後々の誤解やトラブルを避けるために、両家で事前にしっかりとコミュニケーションを取っておくことです。
現代では、主に以下の3つのパターンに分かれることが多いようです。
- 新郎新婦が二人で費用を負担し、自分たちの貯蓄から必要なものを揃える。
- 両家の親が、お祝いとしてそれぞれから同程度の金額を援助する。
- 品物で分担する(例:家電は新婦側、家具は新郎側の親が贈るなど)。
現在の最も一般的な形は、新郎新婦が主体となって準備を進め、親はあくまでそれをサポートする、というスタンスです。親が全てを準備するのではなく、子どもたちの意思を尊重しながら、必要な援助を申し出るのが良いでしょう。
注意点:両家のバランスへの配慮
お祝いしたいという気持ちが強いあまり、片方の親だけが多額の援助を申し出ると、もう片方の親御さんが心理的な負担を感じてしまったり、新郎新婦が恐縮してしまったりする可能性があります。お祝いの気持ちは大切ですが、両家の価値観や経済状況は様々です。新郎新婦を通じて相手方の意向をそれとなく確認するなど、慎重に進めるのが賢明です。
いずれにしても、現代の嫁入り道具は「誰が準備しなければならない」という義務や責任ではありません。大切なのは、娘夫婦の新しい門出を両家で温かく祝福し、彼らがスムーズに新生活を始められるようサポートする気持ちそのものです。
こちらの記事もオススメです(^^)/




結婚する娘に持せる物:具体的な品物リスト
- 結婚する娘に持せるお金の相場
- 結婚する娘に真珠を持せる意味は?
- 結婚する娘に持せる着物と喪服
- 結婚する娘に持せる数珠の必要性
- 母から結婚する娘へプレゼントのアイデア
- 結婚する娘に手作りプレゼントの魅力
結婚する娘に持せるお金の相場

新生活の準備には、家具や家電の購入費用、引っ越し代、新居の初期費用など、何かと物入りなため、「現金」を贈ることは非常に現実的で喜ばれる選択肢です。では、親から娘へ贈る結婚祝いの相場はどのくらいなのでしょうか。
これは、お祝いを渡す目的によって、金額が大きく2つのパターンに分けられます。
1. ご祝儀として現金を贈る場合
結婚式の費用は新郎新婦が自分たちでまかない、親はあくまでゲストの一人としてご祝儀を渡す、というケースです。この場合の金額相場は、10万円~30万円程度が最も一般的とされています。
ただし、これはあくまでも全国的な平均値であり、地域性や各家庭の経済状況、考え方によって様々です。「気持ちだから」と考えるご家庭もあれば、兄弟姉妹間で金額を揃える場合もあります。無理のない範囲でお祝いの気持ちを表すことが何よりも大切です。
ご祝儀の金額は、両家で必ずしも事前にすり合わせて合わせる必要はありません。それぞれの家庭の考え方で決めて問題ないとされていますが、もし気になるようであれば、子どもを通じて相手の意向を尋ねてみても良いでしょう。
2. 結婚式や新生活の費用を援助する場合
結婚式や新生活の準備にかかる費用を親が援助する場合、金額は大きく跳ね上がります。結婚スタイルマガジンの調査によると、親や親族から援助を受けたカップルの援助総額の平均は169.5万円というデータもあり、100万円以上のサポートも決して珍しくありません。
結婚式費用の一部を負担する、新居の敷金礼金を支払う、大型家電一式をプレゼントするなど、援助の形は様々です。この場合は、新郎新婦や相手方の親御さんと事前に「どこまでの費用を」「どのように分担するのか」を明確に話し合っておくことが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。
入籍のみで結婚式を挙げない場合(ナシ婚)
近年増えている「ナシ婚」のカップルにお祝いを贈る場合、ご祝儀の相場は10万円前後が目安となります。あるいは、その予算で新生活に必要な質の良い家具・家電などをプレゼントするのも、形に残り喜ばれるでしょう。
結婚する娘に真珠を持せる意味は?

嫁入り道具として古くから母から娘へと受け継がれてきたものの一つに、真珠(パール)のジュエリーがあります。これは単に美しい装飾品というだけでなく、親が娘の幸せを願う深い意味が込められた、特別な贈り物です。
困難から身を守る「お守り」としての役割
真珠は「月のしずく」「人魚の涙」とも呼ばれ、その清らかな輝きから、古来より持ち主を災いや病気から守る魔除けのお守りとして世界中で大切にされてきました。これから新しい環境へ嫁いでいく娘が、人生の荒波に揉まれることなく、健やかで幸せな人生を送れるように、という母親の切なる願いが込められています。
円満な縁を結ぶ象徴
真珠のネックレスが切れ目なく美しい円を描くその形は、「円=縁」を結ぶとされ、非常に縁起の良いものとされています。夫婦の縁、家族や親戚との縁、そしてこれから出会う人々との新しい人間関係の縁が、円満にどこまでも続いていくように、という想いを託すのに最もふさわしい贈り物の一つです。
大人の女性の「嗜み」としての必需品
そして、実用的な側面も非常に大きいです。良質なパールの一連ネックレスとイヤリング(またはピアス)のセットは、結婚式や入学式といったお祝いの席から、お悔やみの席まで、冠婚葬祭のあらゆるフォーマルな場面で使える万能なジュエリーです。
社会人として、そして家庭を持つ一人の女性として、きちんとした装いが求められる場面は必ず訪れます。その時に、質の良いパールジュエリーは娘さんの品格を高め、自信を与えてくれる、まさに一生もののお守りとなるでしょう。
真珠は汗や酸に弱いデリケートな宝石です。贈る際には「使った後は必ず柔らかい布で拭いてからしまうのよ」と、お手入れの方法も一緒に教えてあげると、より愛情が伝わりますし、永く美しく使ってもらえますよ。
結婚する娘に持せる着物と喪服

伝統的な嫁入り道具の代表格であった着物ですが、現代の生活では「着る機会がほとんどない」「保管や手入れが大変」といった現実的な理由から、豪華な着物一式をあつらえるケースは大幅に減少しています。
しかし、その中でも「喪服」だけは、いざという時のために準備しておくと良い、と考える親御さんは今でも少なくありません。
なぜ喪服を準備しておくことが大切なのか
お悔やみ事は、季節や時間を問わず、ある日突然やってきます。特に結婚して家庭を持つと、自分たちの親族だけでなく、パートナーの親族や職場関係など、お付き合いの範囲が広がり、急な弔問の機会も増える可能性があります。
そのような時に、慌ててレンタルショップを探したり、量販店で間に合わせの質の良くないものを購入したりすることがないように、あらかじめ自分の体に合ったきちんとした喪服を準備しておくことは、社会人として、そして大人の女性としての重要な嗜みであり、心の安心材料になります。
準備する喪服の種類とポイント
- 洋装(ブラックフォーマル): 現在はこれが一般的です。季節を問わず着用できる長袖のワンピースとジャケットのアンサンブルタイプが一着あると、一年を通して対応でき非常に便利です。
- 和装(黒無地五つ紋): 実家や嫁ぎ先がしきたりを重んじる家柄の場合や、本人が希望する場合には、染め抜きの五つ紋が入った黒無地の和装の喪服を用意しておくと、より格式高く丁寧な印象になります。
喪服は、決して頻繁に袖を通すものではありません。だからこそ、いざという時に娘が困らないように、慌てないようにという親心から贈られる、非常に実用的な愛情の形と言えるでしょう。
結婚する娘に持せる数珠の必要性

喪服とセットで、ぜひ準備しておきたいのが「数珠(じゅず)」です。これもまた、社会人として、そして家庭を持つ一人の大人として、フォーマルな場で自分を表現するために持っておくべき大切な道具の一つです。
数珠は個人の「お守り」であり、貸し借りはしないもの
数珠は、単なる仏具ではなく、仏様と心を通わせるための大切な法具であり、持ち主個人の分身であり、お守りとされています。そのため、たとえ親子や夫婦であっても、数珠の貸し借りはしないのが正式なマナーです。
結婚という人生の大きな節目を機に、娘さん専用のきちんとした数珠を持せてあげることは、「これからは新しい家庭を築く一人の人間として、社会的な責任を果たしていくのですよ」という、親からの無言のメッセージにもなります。
数珠には様々な素材やデザインのものがあります。宗派によって正式な形が異なる場合もありますが、特にこだわりがなければ、どの宗派でも共通で使える「略式数珠」を一つ持っておくと、ほとんどの場面で対応できるのでおすすめです。誕生石や好きな色の天然石(水晶、瑪瑙、翡翠など)で作られた美しいものも多く、お守りとして長く大切にしてもらえますよ。
急な弔事に備えるための「一式セット」
前述の通り、お葬式は突然訪れるものです。その際に、喪服はあっても数珠がないと、非常に心もとなく感じてしまいます。喪服、数珠、袱紗(ふくさ)、黒いフォーマルバッグ、黒いパンプスなどを一式で揃えて専用のケースに入れて持せてあげると、娘さんもいざという時に慌てず、安心して新しい生活をスタートできるでしょう。
このように、すぐに使うものではなくても、社会生活を送る上で「いざという時に必要になるもの」をきちんと準備してあげるのが、親として最後にできる大切な支度なのかもしれません。
母から結婚する娘へプレゼントのアイデア

これまでに紹介した伝統的かつ実用的な品々の他にも、母親から娘へ贈るプレゼントには、愛情を形にする様々な選択肢があります。娘さんの幸せな未来を願う気持ちを込めた、素敵なアイデアをいくつかご紹介します。
新しい姓を刻む「印鑑」~人生の節目を応援する贈り物~
結婚によって姓が変わる娘さんへ、新しい姓を刻んだ印鑑を贈るのも、非常に意味深く実用的なプレゼントです。印鑑は、銀行口座の開設や不動産の契約など、人生の重要な場面で必要となる、まさにその人自身を証明し、社会的な責任を表明する「しるし」です。
これから始まる新しい人生の様々な場面で、娘さんを守り、幸せな未来への扉を開く後押しをしてくれるお守りとなるでしょう。長く使えるよう、少し良い材質(象牙やチタン、天然石など)のものを選び、実印・銀行印・認印の3本セットで贈ると、より一層喜ばれ、様々なシーンで役立ちます。
新生活を彩る上質なキッチン用品
「美味しいものをたくさん作って、温かい家庭を築いてほしい」そんな願いを込めて、日々の暮らしに役立つプレゼントも人気です。例えば、高性能なブレンダーや電気圧力鍋といった便利な調理家電や、有名ブランドの包丁、夫婦で使えるペアのお箸や美しいデザインの食器セットなどが挙げられます。
毎日使うものだからこそ、少し質の良いものを選ぶことで、日々の暮らしが豊かになり、料理をする時間も楽しくなるはずです。
母から娘へ受け継がれるジュエリー
もしお母様が大切にしているジュエリーがあれば、それを譲るというのも他にはない素敵な選択肢です。例えば、おばあ様から受け継いだ婚約指輪を現代的なデザインにリフォームして贈ったり、自分が使っていたネックレスを綺麗に磨き直してプレゼントしたり。そこには、家族の歴史や愛情、想い出が詰まっており、お金では買うことのできない、かけがえのない贈り物になります。
結局のところ、大切なのは金額や豪華さではありません。娘さんの性格やライフスタイルを一番よく知る母親だからこそ選べる、新生活に心から寄り添う気持ちを込めた品物こそが、何よりのプレゼントになるのです。
結婚する娘に手作りプレゼントの魅力

市販の品物を贈るのももちろん素晴らしいことですが、もしお母様に時間と手間をかける余裕があるのなら、世界に一つだけの心のこもった手作りのプレゼントは、他にはない特別な贈り物になります。
既製品にはない手作りの品に込められた温もりは、何物にも代えがたい価値を持ち、きっと娘さんの心に深く、そして永く残る宝物になるでしょう。
時間と愛情がダイレクトに伝わる
手作りプレゼントの最大の魅力は、なんといっても作り手である母親の愛情や費やした時間が、そのまま形となってダイレクトに伝わることです。娘さんの喜ぶ顔を思い浮かべながら、一針一針布を縫ったり、一つひとつパーツを組み立てたりする時間は、親にとってもかけがえのない幸せな時間となります。
その制作のプロセスそのものが、言葉以上に雄弁な娘さんへの愛情表現であり、完成した品は、どんな高級ブランド品にも負けない価値を持つ、世界に一つだけの宝物になるのです。
愛情を形にする手作りプレゼントの具体例
手作りプレゼントのアイデア
- リングピロー: 結婚式で指輪を交換する際に使うリングピローは、比較的小さく、裁縫がそれほど得意でない方でも挑戦しやすい人気のアイテムです。
- ウェルカムボード: 披露宴会場の入り口でゲストを迎えるウェルカムボードも素敵です。押し花やカリグラフィー、イラストなど、お母様の得意なことを活かして作ることができます。
- 花嫁用のアクセサリー: 小さなブローチや髪飾り、ベールなど、花嫁衣装にそっと添えられる手作りのアクセサリーも、個性的で心のこもった贈り物になります。
- 思い出のアルバムや手紙: 生まれてからこれまでの思い出の写真を一冊のアルバムにまとめ、そこに心のこもった手紙を添える。これは、最もシンプルで、最も感動的なプレゼントの一つです。
手作りの品を贈る際に一つだけ注意したいのは、それが自己満足にならないようにすることです。デザインの好みや結婚式のテーマなどを事前にさりげなくリサーチし、娘さんが本当に喜んで使ってくれるものを作るよう心がけましょう。
たとえ少し不格好だったり、プロのようにはいかなかったりしても、母親が自分のために時間と愛情をかけて作ってくれたという事実は、これからの長い結婚生活の中で、時に娘さんを励まし、温かく支えてくれる最高のお守りになるはずです。
後悔しない結婚する娘に持せる物の選び方
- 嫁入り道具は新生活を支える実用的な品が中心
- トレンドは冷蔵庫や洗濯機などの大型家電や質の良い家具
- 令和のスタイルは本当に必要なものだけを厳選するミニマムな考え方
- 自分たちのセンスで選べる現金や商品券も合理的で喜ばれる選択肢
- 伝統的な嫁入り道具は家の格式や親の深い愛情を示す意味があった
- 結納金なしの場合は両家のバランスを考え話し合いで援助の形を決めることが重要
- ご祝儀として現金を贈る場合の一般的な相場は10万円から30万円が目安
- 結婚費用を援助する場合は100万円以上になることも珍しくない
- 真珠のジュエリーは「お守り」と「大人の嗜み」として一生ものの贈り物になる
- 着物一式は不要でも自分の体に合った喪服だけは準備しておくと安心
- 数珠は個人の持ち物であり結婚という節目に持せるのが良い
- 新しい姓を刻む印鑑は娘の新しい人生を応援する象徴的なプレゼント
- 手作りのプレゼントは時間と愛情が伝わるかけがえのない贈り物になる
- 最も大切なのは豪華さや金額ではなく娘の幸せを願う親の気持ち
- 何を贈るかはサプライズにこだわらず必ず本人とよく相談して決める
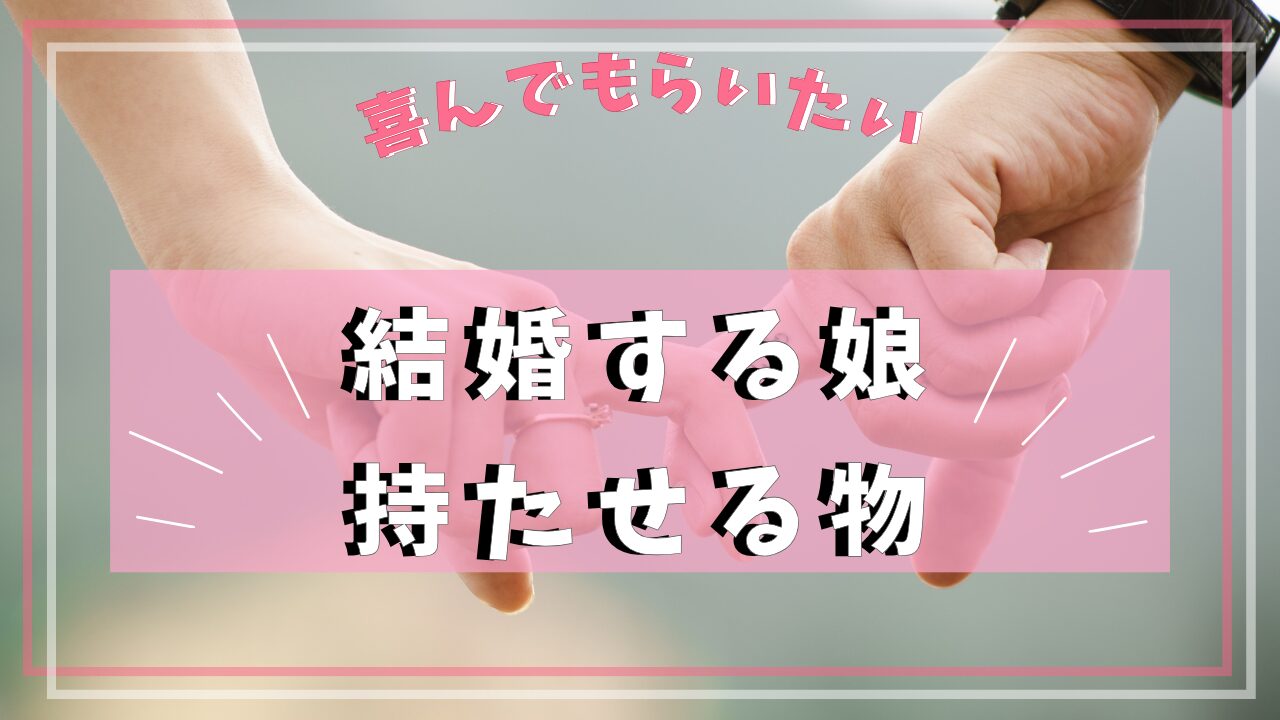
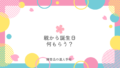

コメント