夏の定番和菓子の餅とは?贈答品におすすめの選び方
夏の定番和菓子の餅と聞いて、あなたはどのようなお菓子を思い浮かべますか?夏の餅といえば、土用の時期に食べるあんころ餅や、ぷるぷるとした食感が楽しいわらび餅が有名です。しかし、夏の和菓子といえば、涼やかな水菓子も欠かせません。
この記事では、夏の風物詩であるお餅はもちろん、みずみずしい寒天を使ったお菓子や、食べるのがもったいないほど美しい練り切りまで、夏におすすめの和菓子を一覧でご紹介します。贈答品選びの参考になる人気ランキングの情報も交えながら、その魅力に迫りますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 夏の定番とされるお餅の種類とその由来
- お餅以外の夏を代表する和菓子の特徴
- 贈答品選びの参考になる人気の和菓子
- 夏に和菓子をより美味しく楽しむためのポイント
夏の定番和菓子の餅の基本と選び方
- 夏の定番和菓子の餅は何ですか?
- 夏の餅は?土用餅やわらび餅が有名
- 夏の餅といえば無病息災を願う土用餅
- 夏を代表する和菓子は?一覧で紹介
- 夏の和菓子といえば涼やかな水菓子
夏の定番和菓子の餅は何ですか?

夏の定番和菓子の餅として、古くから日本の四季と暮らしの中に溶け込んできた代表的なものに「土用餅(どようもち)」と「わらび餅」が挙げられます。これらは単なる甘味ではなく、それぞれが持つ背景や文化的な意味合いが、夏の風物詩としての地位を確立させています。
土用餅は、夏の土用(立秋前の約18日間)という、一年で最も暑さが厳しいとされる時期に食される伝統的なあんころ餅です。この習慣の根底には、厳しい夏を健やかに乗り越えたいという人々の切実な願いがあります。餅は古来よりエネルギーの源である「力餅」として、そして小豆の鮮やかな赤い色には邪気を払う力があると信じられてきました。つまり、土用餅は、夏バテ防止のスタミナ食と厄除けのお守りの二つの意味を持つ、先人の知恵が詰まった和菓子なのです。
一方、わらび餅は、その涼やかな見た目と食感で五感に訴えかける、夏の甘味の代表格です。ぷるぷると震えるような独特の弾力と、ひんやりとした口当たりは、蒸し暑い日本の夏に一時の清涼感をもたらしてくれます。きな粉の香ばしさや黒蜜の深い甘みとの相性も抜群で、時代を超えて多くの人々に愛され続けています。
このように、夏の餅には季節の風習に根差したものと、涼やかさや食感そのものを楽しむものがあり、それぞれに異なる魅力があります。贈答品として選ぶ際には、相手の好みはもちろんのこと、こうした文化的な背景を知っておくと、より一層心のこもった、物語のある贈り物になるでしょう。
夏の定番和菓子の餅のポイント
土用餅:夏の土用の時期に、厳しい暑さを乗り切るための無病息災を願って食べられる、文化的な背景を持つあんころ餅。
わらび餅:ひんやりとした独特の食感と喉越しが五感で涼を楽しませてくれる、夏の代表的な餅菓子。
夏の餅は?土用餅やわらび餅が有名

前述の通り、夏の餅として特に有名なのは土用餅とわらび餅ですが、それぞれの特徴をさらに深く掘り下げて見ていきましょう。素材へのこだわりや、地域に根付いた多様な夏の餅文化も存在します。
土用餅
土用餅は、滑らかなこし餡でつきたてのお餅を包んだ、シンプルながらも奥深い和菓子です。夏の土用の時期は、気候の変動が激しく体調を崩しやすいことから、古くから「養生」が大切にされてきました。栄養価の高いお餅は手軽なエネルギー源となり、小豆にはビタミンB1などが含まれているとされています。江戸時代頃から始まったとされるこの風習は、厳しい季節を乗り切るための合理的な食習慣でもあったのです。
わらび餅
わらび餅の魅力は、その比類なき食感にあります。本来の原料である「本わらび粉」は、野生のワラビの地下茎を叩き、洗い、何度も精製を繰り返して作られる非常に貴重なデンプンです。一説には、ワラビの根10kgからわずか70g程度しか採れないとも言われるほど手間暇がかかるため、本わらび粉100%で作られたわらび餅は、とろけるような口溶けと独特のコシを持つ最高級品として扱われます。現在市場に流通しているものの多くは、さつまいもやタピオカのデンプン(甘藷澱粉など)が使われていますが、それぞれの配合によって異なる食感を楽しむことができます。
豆知識:半夏生餅(はげっしょうもち)
奈良県や大阪府の一部地域には、夏至から11日目にあたる「半夏生(7月2日頃)」に、田植えの重労働をねぎらい、稲がタコの足のようにしっかりと根付くことを願って「半夏生餅」を食べる風習が今も残ります。農林水産省の「うちの郷土料理」によると、これは小麦ともち米を合わせてつき、きな粉をまぶしたお餅で、「さなぶり餅」とも呼ばれ、農作業の一区切りを祝う大切な行事食です。(出典:農林水産省「うちの郷土料理」)
夏の餅といえば無病息災を願う土用餅

夏の餅の代表格である土用餅は、単なる季節のお菓子という枠を超え、日本の暦や思想と深く結びついています。「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前約18日間を指す雑節のことで、古代中国の五行思想(万物は木・火・土・金・水の5つの元素からなるという考え)に由来します。季節の変わり目であるこの期間は、気が乱れやすく、体調に変化をきたしやすいとされてきました。
特に夏の土用は暑さが最も厳しく、夏バテや病気にかかりやすい時期。そこで、「丑(うし)の日」に「う」の付くものを食べると夏負けしないという言い伝えが生まれました。「うなぎ」がその代表ですが、「うし」にちなんで小豆(あんこ)を牛の肝に見立てて食べるという説や、餅を力餅として食べる習慣が結びつき、「土用餅」が広まったと考えられています。
「土用の丑の日」に鰻を食べるのは有名ですが、土用餅の風習をご存知でしたか?実はこの風習、江戸時代の文献にも登場するほど歴史があるんですよ。お店によっては、この時期限定で特別なこし餡を使ったあんころ餅が並びます。ひんやりとした麦茶や、さっぱりとした水出しの煎茶と一緒にいただくと、夏の疲れがすっと癒やされるような気がします。
このように言うと、土用餅が非常に特別なものに感じられますが、基本的にはお餅とあんこという、日本人が愛する素朴な組み合わせです。だからこそ、小豆の種類や炊き方、餅のつき加減といった、和菓子店の基本的な技術とこだわりが味を大きく左右します。老舗和菓子店の丁寧に作られた土用餅は、夏の贈り物としても格別な一品となるでしょう。
こちらの記事もオススメです(^^)/


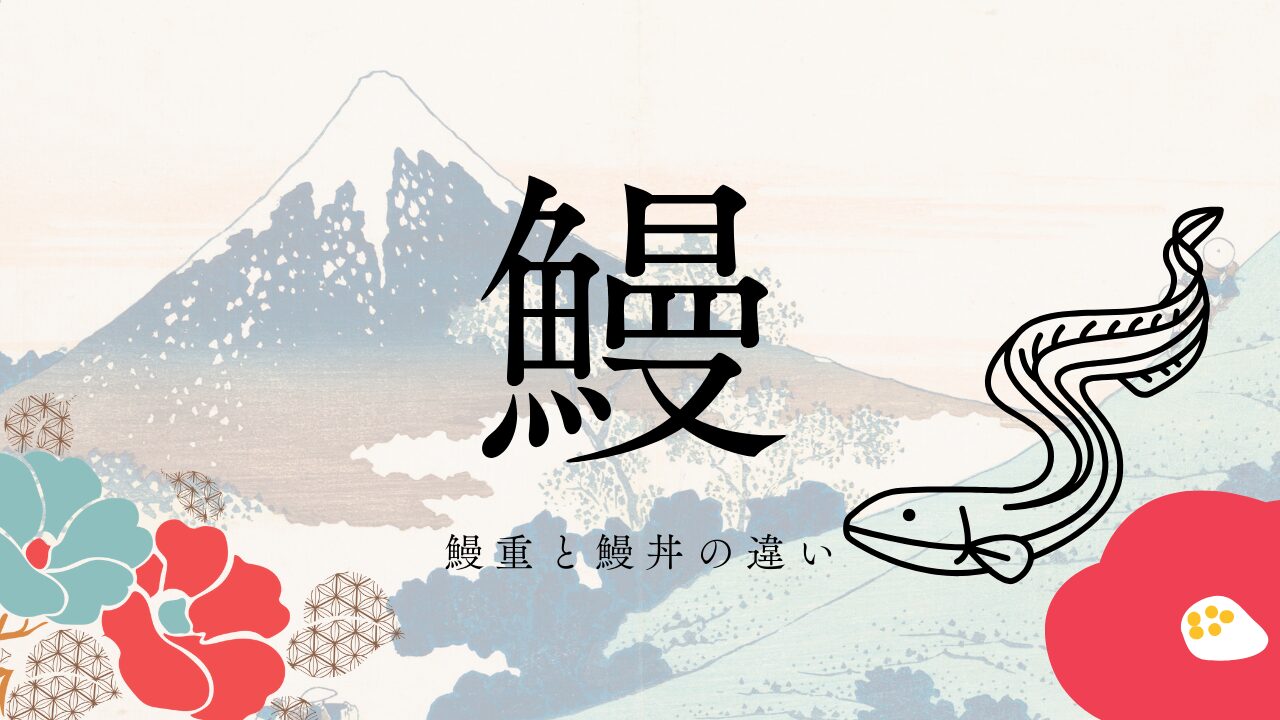

夏を代表する和菓子は?一覧で紹介

夏は餅菓子以外にも、五感で涼を感じられる、魅力的な和菓子が数多く存在します。ここでは、夏を代表する和菓子を、その文化的背景や楽しみ方と共に一覧でご紹介します。贈答品選びや、ご自宅でのティータイムの参考にしてみてください。
| 和菓子名 | 主な特徴 | 由来や関連行事 | 楽しみ方 |
|---|---|---|---|
| 水羊羹(みずようかん) | 通常の練り羊羹よりも寒天の量を減らし、水分を多くして作られる。みずみずしく、つるんとした喉越しが特徴。 | 元々はおせち料理の一品として冬に作られていたものが、製氷技術の発達により夏に冷やして食べる菓子として定着した。 | 冷蔵庫でよく冷やし、涼やかなガラスの器でいただくのがおすすめ。竹筒に入った風流なものも人気。 |
| 葛まんじゅう(くずまんじゅう) | 本葛粉で作った透明度の高い生地であんを包んだお菓子。ぷるんとした弾力と、なめらかな口当たりが魅力。 | 水の都として知られる岐阜県大垣市が発祥とも言われ、豊富な地下水で冷やして食されたことが始まりとされる。 | 冷たい清流を思わせるように、冷水に浮かべて提供されることもあり、究極の清涼感を楽しめる。 |
| 若鮎(わかあゆ) | 鮎をかたどった薄いカステラ風の焼き生地で、餅の一種である求肥(ぎゅうひ)を包んだ焼き菓子。 | 鮎釣りが解禁となる初夏から夏にかけての季節菓子。夏の訪れを告げる風物詩として親しまれる。 | ほんのり甘い生地ともちもちの求肥のコントラストが楽しい。冷たい緑茶やほうじ茶との相性が良い。 |
| 水無月(みなづき) | 白いういろう生地の上に甘く煮た小豆をのせ、三角形に切った京都の伝統菓子。 | 一年の半分にあたる6月30日に行われる神事「夏越の祓(なごしのはらえ)」で、残り半年の無病息災を祈って食べられる。 | 三角形は暑気を払う氷を、小豆は悪魔払いを意味する。歴史や文化を感じながらいただきたい縁起菓子。 |
| くずきり | 葛粉を水で溶いて加熱し、板状に固めたものを細長く切ったもの。黒蜜やきな粉をかけて食す。 | 京都の祇園が発祥とされ、江戸時代から愛されてきた甘味。元々は宮中の饗宴料理だったとも言われる。 | 注文を受けてから作るお店も多く、できたての瑞々しい食感とコシは格別。夏の贅沢なデザート。 |
| あんみつ | 角切りの寒天を主役に、あんこ、求肥、フルーツ、赤えんどう豆などを彩りよく盛り合わせた甘味。 | 銀座の甘味処が発祥とされる「みつ豆」にあんこをのせたものが始まり。昭和初期に誕生した比較的新しい和菓子。 | アイスクリームや白玉をトッピングするなど、アレンジは無限大。自分好みの組み合わせを見つけるのも楽しい。 |
夏の和菓子といえば涼やかな水菓子

夏の和菓子を語る上で欠かすことのできないカテゴリが「水菓子(みずがし)」です。この言葉の響きだけでも、清らかな水の流れや瑞々しい潤いが感じられます。本来、歴史的に「水菓子」は果物全般を指す言葉でした。しかし、時代と共にその意味は広がり、現代では水羊羹や葛菓子、フルーツを使ったゼリーなど、水分を豊富に含み、ひんやりとした喉越しが楽しめる菓子の総称としても広く使われています。
水菓子の最大の魅力は、その名の通り、喉を潤すような瑞々しさと、涼を運ぶ清涼感にあります。厳しい暑さで食欲が落ちがちな夏でも、つるんと食べられるものが多く、体の中から優しく涼を取ることができます。デザートやおやつとしてはもちろん、食欲のない時の栄養補給としても重宝されます。
水菓子の魅力
- 喉越しの良さ:つるんとした食感で、食欲がない時でも食べやすい。
- 見た目の涼やかさ:透明な素材やガラスの器を使い、視覚的に涼を演出。
- 旬の味わい:夏のフルーツを使ったものは、季節感も楽しめる。
また、水菓子は見た目の美しさも特徴の一つです。ガラスの器に涼しげに盛り付けられたり、錦玉羹のように中に金魚や紅葉の形をした羊羹を沈めたりと、まるで芸術品のような工夫が凝らされています。これらの水菓子は、お中元や夏の手土産としても非常に人気が高く、贈られた相手に涼しいひとときと感動を届けることができる、夏のギフトの主役です。
こちらの記事もオススメです(^^)/

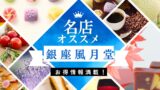

贈答品にも!夏の定番和菓子の餅と関連菓子
- つるんとした食感が魅力の寒天菓子
- 芸術的な美しさで魅せる練り切り
- 和菓子の定番のランキングは?
- 人気の夏の和菓子ランキングを紹介
- 贈答品にも喜ばれる夏の定番和菓子の餅
つるんとした食感が魅力の寒天菓子

夏の和菓子に涼やかさと独特の食感をもたらす重要な素材が「寒天」です。テングサやオゴノリといった海藻を原料とする寒天は、日本の伝統的な食材であり、その製造方法は自然の力を利用したものです。冬の厳しい寒さの中で、煮溶かしたテングサを戸外で凍結させ、日中の太陽で解凍・乾燥を繰り返すことで、水分が抜けて食物繊維が凝縮されます。この「天然凍結製法」によって、独特の歯切れの良い食感が生まれるのです。
厚生労働省が運営する健康情報サイト「e-ヘルスネット」によると、寒天は食物繊維を非常に多く含む食品として紹介されています。こうした背景もあり、健康志向の方にも注目されています。(出典:e-ヘルスネット(厚生労働省)「食物繊維の働きと1日の摂取量」)
寒天を使った代表的な夏の和菓子が、あんみつや水羊羹、そして錦玉羹です。特に錦玉羹(きんぎょくかん)は、寒天の高い透明性を最大限に活かした「食べる宝石」ともいえるお菓子。中に色とりどりの羊羹で作った金魚や季節の花を閉じ込め、まるで水の中の美しい景色をそのまま切り取ったかのようなデザインは、見ているだけでも涼しい気分にさせてくれます。
ところてんとくずきりの違いを再確認
見た目が似ているため混同されがちな「ところてん」と「くずきり」ですが、原料が全く異なります。「ところてん」はテングサを煮溶かして冷やし固めたもので、磯の香りと独特の歯ごたえが特徴です。一方、「くずきり」は葛粉から作られており、よりなめらかで弾力のある食感が楽しめます。用途も異なり、ところてんは酢醤油などで食事としても食されるのに対し、くずきりは黒蜜などをかけて甘味としていただくのが一般的です。
あんみつは、そんな寒天そのものの食感を主役として楽しむ和菓子です。角切りにされた寒天のぷりっとした食感に、あんこの甘さ、フルーツの酸味、赤えんどう豆の塩気が絶妙なハーモニーを奏でます。具材の組み合わせ次第で無限のバリエーションが楽しめるのも、あんみつの奥深い魅力の一つです。
芸術的な美しさで魅せる練り切り

「練り切り(ねりきり)」は、上生菓子を代表する存在であり、和菓子の世界における美の結晶とも言えるものです。主原料である白あんに、つなぎとして求肥(ぎゅうひ)や山の芋、みじん粉などを加えて練り上げた「練り切りあん」は、粘土のように滑らかで、非常に細やかな細工に適した性質を持ちます。この特性を活かし、職人は季節の移ろいや自然の美しさを菓子の上に表現します。
その最大の特徴は、茶の湯の文化と深く結びつき、季節感を何よりも重んじる繊細で芸術的な意匠にあります。職人は木型やヘラ、布巾、そして自らの指先を巧みに使い、一つひとつに命を吹き込むように手作業で作り上げます。その創作の源泉は、和歌や俳句、絵画など、日本の伝統文化全般に及びます。
夏には、涼を呼ぶモチーフが選ばれます。
- 朝顔:夏の朝の清々しさを象徴します。
- 金魚:水の中を優雅に泳ぐ姿が、涼やかさを演出します。
- 撫子(なでしこ):可憐な花の姿が、奥ゆかしい日本の夏を思わせます。
- 清流:岩間を流れる水のきらめきや冷たさを表現します。
- 花火:夏の夜空を彩る一瞬の輝きと儚さを菓子に閉じ込めます。
これらの練り切りは、まさに「食べる芸術」であり、お茶席やおもてなしの場を華やかに彩る主役です。口に含めば、なめらかで上品な甘さが静かに広がり、見た目の美しさだけでなく、味わいも一級品であることを実感させてくれます。餅菓子や水菓子とは異なるアプローチで「涼」を表現する練り切りは、季節感を大切にする方や、目上の方への特別な贈り物として、この上ない選択肢と言えるでしょう。
和菓子の定番のランキングは?

夏の和菓子に話を絞る前に、まずは季節を問わず、年間を通して日本人に愛され続けている和菓子の定番について理解を深めてみましょう。様々な調査がありますが、その多くで上位に挙がるのは、長い歴史の中で私たちの生活に深く根付いてきたお菓子たちです。
- 大福・餅菓子:もちもちとした食感と、あんこやフルーツなど中身の多様性が人気の理由。豆大福やいちご大福は特に根強い人気を誇ります。
- どら焼き:ふんわりと焼き上げた生地であんこを挟んだ、シンプルながらも満足感の高いお菓子。手軽なおやつとして、また手土産としても万能です。
- 羊羹:贈答品の王道。しっかりとした甘さと日持ちの良さから、古くから贈り物として重宝されてきました。老舗の高級なものから、手軽な一口サイズまで様々です。
- せんべい・おかき:甘いものが苦手な方にも喜ばれる、米を原料とした塩味の和菓子。醤油や海苔、ザラメなど味のバリエーションも豊かです。
- カステラ:厳密にはポルトガルから伝わった南蛮菓子ですが、日本で独自の進化を遂げ、しっとりとした食感と上品な甘さで和菓子として完全に定着しています。
これらの和菓子が定番として愛される理由は、美味しさはもちろんのこと、その「安定感」と「文化的背景」にあります。スーパーやコンビニで日常的に手に入る手軽さがありながら、一方で「とらやの羊羹」や「鎌倉豊島屋の鳩サブレー」、「文明堂のカステラ」のように、特定の地域や店舗を代表する「銘菓」として、ハレの日の贈答品ランキングで常に上位に名を連ねるブランド力も兼ね備えています。
ここでご紹介したのは、年間を通した和菓子全体の人気ランキングの一例です。これらの定番和菓子の中にも、夏限定のフレーバー(例えば、塩レモン味のどら焼きなど)が登場することがあります。次の見出しでは、いよいよ「夏」という季節に特化した人気の和菓子を、より具体的にご紹介します。
人気の夏の和菓子ランキングを紹介

それでは、お待たせしました。ここではギフト選びの専門ECサイトや全国の百貨店の販売実績などを参考に、特に夏に人気が集まるトレンドの和菓子をランキング形式でご紹介します。お中元や帰省土産など、大切な方への贈答品選びの際にぜひお役立てください。
第1位:わらび餅
夏の和菓子として、やはり不動の人気を誇るのがわらび餅です。ぷるんとした独特の食感と、きな粉や黒蜜の優しい甘さは、子どもから大人まで幅広い世代に愛されます。特に近年は、希少な本わらび粉を使用した、とろけるような口溶けの名店のわらび餅が注目を集めており、お取り寄せスイーツとしても人気が沸騰しています。特別な方への贈り物として、格別の満足感を提供できる一品です。(参照:吉野本葛 天極堂 公式オンラインショップなど)
第2位:水羊羹・あんみつ羊羹
ひんやりと冷やしていただく水羊羹も、夏の贈答品の定番中の定番です。なめらかな喉越しと小豆の上品な甘さは、夏の疲れた心と身体を優しく癒してくれます。最近のトレンドとして、伝統的な水羊羹だけでなく、寒天や求肥、大粒の栗などを贅沢に閉じ込めた、あんみつのような豪華な羊羹も人気を集めています。切り分けるたびに現れる美しい断面も魅力の一つです。(参照:麻布昇月堂 公式サイト「一枚流し麻布あんみつ羊かん」など)
第3位:フルーツを使った和菓子
夏が旬のフレッシュなフルーツをまるごと使った、見た目にも華やかな和菓子も非常に人気があります。白餡との相性が絶妙なフルーツ大福(シャインマスカット、桃、パイナップルなど)や、果実をくりぬいて器にし、果汁をたっぷり使ったくりぬきゼリーは、そのインパクトと瑞々しさで、贈られた相手に驚きと感動を与えます。和と洋の垣根を越えた、新感覚の夏の涼菓です。(参照:老松 公式サイト「夏柑糖」など)
第4位:錦玉羹などの創作和菓子
見た目の美しさや芸術性で選ぶなら、錦玉羹などの創作和菓子は外せません。「天の川」や「金魚すくい」といった夏の情景を、寒天の中に詩的に表現した季節限定の和菓子は、食べるのが惜しくなるほどの芸術品です。涼やかな見た目は、SNSなどでも大きな注目を集め、話題性のある贈り物としても喜ばれます。(参照:七條甘春堂 公式オンラインショップ「天の川」など)
贈答品にも喜ばれる夏の定番和菓子の餅
この記事では、夏の定番和菓子の餅を中心に、夏にぴったりの様々な和菓子とその文化的背景、選び方のポイントをご紹介してきました。最後に、記事の要点をまとめます。
- 夏の定番和菓子の餅は主に「土用餅」と「わらび餅」
- 土用餅は夏の土用の時期に無病息災を願って食べるあんころ餅
- 餅は力をつけ、小豆の赤は厄除けの意味を持つとされる
- わらび餅はひんやりとした喉越しとぷるぷるの食感が人気
- 夏の和菓子は水分が多く涼やかな「水菓子」も代表的
- 水菓子には水羊羹、葛まんじゅう、錦玉羹などがある
- 寒天はあんみつや錦玉羹に使われ、見た目と食感で涼を演出する
- 練り切りは「食べる芸術」と呼ばれ、夏の風物詩が表現される
- 若鮎や水無月など、特定の季節や行事にちなんだ和菓子も豊富
- 贈答品選びでは、見た目の涼やかさや季節感が重要なポイントになる
- 老舗の和菓子や、旬のフルーツを使ったものは特に喜ばれる傾向にある
- お中元や暑中見舞い、帰省の手土産に夏の和菓子は最適
- 和菓子をいただく際は、冷蔵庫で適度に冷やすとより美味しくなる
- 贈り物にする際は、相手の好みや家族構成を考慮し、賞味期限も確認する
- この記事を参考に、あなたにぴったりの夏の和菓子を見つけてほしい



コメント