もうすぐ敬老の日ですね。保育園に通う0歳児や1歳児、2歳児、3歳児のお子さんが、心を込めてプレゼントを製作する姿を想像すると、温かい気持ちになるものです。定番のハガキをはじめ、様々な製作のアイデアがありますが、「うちの子でも大丈夫かな?」「子ども簡単にできる手作りのものはある?」といった疑問や、年齢に合ったプレゼント選びに関する不安を感じる保護者の方も少なくないでしょう。この記事では、保育園で作る敬老の日のプレゼントについて、ねらいから年齢別の具体的なアイデアまで詳しく解説します。
- 敬老の日の基本的な知識や保育園でのねらい
- 子どもが簡単に作れる手作りプレゼントの具体例
- 0歳児から3歳児までの年齢に合わせた製作のポイント
- プレゼント作りにおける保護者の関わり方や注意点
保育園の敬老の日プレゼント|0.1.2.3歳児向け情報
- そもそも敬老の日ってなに?
- 子供は何歳から敬老の日の対象になりますか?
- 保育園で敬老の日を行う狙いは?
- 敬老の日の製作のねらいについて
- 子ども簡単な手作り敬老の日プレゼント
そもそも敬老の日ってなに?

敬老の日は、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことを目的とした国民の祝日です。毎年9月の第3月曜日に制定されており、おじいちゃんやおばあちゃんへ感謝の気持ちを伝え、これからの健康と長寿を願う大切な日として、日本全国で親しまれています。
この祝日の起源は、1947年に兵庫県のある村で始まった「としよりの日」に遡ると言われています。当初は農閑期で気候も良い9月15日に設定され、お年寄りを大切にする行事として始まりました。これが徐々に全国へと広がり、1966年に国民の祝日「老人の日」として正式に制定されます。
その後、祝日法改正、いわゆるハッピーマンデー制度の導入により、2003年からは現在の「9月第3月曜日」に移動し、名称も「敬老の日」へと変更されました。日付は変わりましたが、人生の先輩であるお年寄りを敬い、感謝するという本来の趣旨は、今も変わらず受け継がれています。家庭や地域で食事会を開いたり、プレゼントを贈ったりと、様々な形でお祝いが行われる日となっています。
こちらの記事もオススメです(^^)/
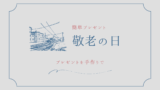
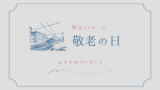
子供は何歳から敬老の日の対象になりますか?

敬老の日のお祝いを「何歳から始めるか」という点について、法律などで定められた明確な決まりは一切ありません。したがって、お祝いする側の気持ち次第で、何歳の方をお祝いしても間違いではないと考えられます。
ただ、一つ注意したいのは、お祝いされる側の気持ちです。近年は60代、70代でも非常に若々しく、現役で活動されている方が多くいらっしゃいます。そのような方に対して「敬老」という言葉を使うと、「年寄り扱いされた」と感じ、かえって複雑な気持ちにさせてしまう可能性も否定できません。
一般的には、孫が生まれたタイミングをきっかけにおじいちゃん・おばあちゃんとしてお祝いを始めたり、還暦(60歳)や古希(70歳)といった長寿祝いの節目を機にしたりするケースが多いようです。
最も大切なのは、年齢という形式にこだわることではなく、相手を思いやる心です。もし迷うようであれば、プレゼントを贈る前に「日頃の感謝を伝えたくて」と思いを伝えてみたり、お孫さんからのプレゼントとして渡したりすると、自然に受け取ってもらいやすいかもしれません。
保育園で敬老の日を行う狙いは?

保育園で敬老の日に関連する活動を行うことには、子どもたちの成長にとっていくつかの大切な狙いがあります。単にプレゼントを作るという作業だけでなく、その過程を通して多くのことを学ぶ機会となるのです。
一つ目の狙いは、日本の伝統文化に親しむことです。敬老の日は古くから続く日本の大切な文化の一つであり、子どもたちがその意味や由来に触れることで、自国への関心や理解を深めるきっかけになります。
二つ目は、身近な人への感謝の気持ちを育むことです。いつも自分たちを見守り、優しくしてくれるおじいちゃんやおばあちゃんの存在を改めて意識させます。そして、「ありがとう」「いつまでも元気でいてね」という気持ちを、プレゼント作りという具体的な行動を通して表現する経験は、思いやりの心を豊かにするでしょう。
さらに、異世代との交流の機会を生み出すという側面もあります。プレゼントを渡す際に、おじいちゃんやおばあちゃんと直接触れ合うことで、子どもたちは自分たちとは違う世代の考え方や温かさに触れることができます。これは、子どもたちの社会性を育む上で非常に貴重な体験と言えます。このように、保育園での敬老の日の活動は、子どもたちの心を多方面から豊かにする教育的な意義を持っています。
敬老の日の製作のねらいについて

前述の通り、保育園で敬老の日の行事を行うことには様々な狙いがありますが、その中心的な活動である「製作」にも、子どもたちの発達を促す具体的なねらいが込められています。
まず挙げられるのが、指先の巧緻性(こうちせい)を高めることです。クレヨンで絵を描いたり、シールを貼ったり、紙をちぎったりといった作業は、一見簡単に見えますが、0歳から3歳頃の子どもたちにとっては指先の細かな動きをコントロールする良い訓練になります。これらの活動を繰り返すことで、脳の発達も促されると考えられています。
次に、創造力や表現力を養うというねらいです。何色の折り紙を使おうか、どこにシールを貼ろうかと考えながら作る過程は、子どもたちの自由な発想を引き出します。完成した作品は、たとえ大人の目から見て整っていなくても、その子なりの「大好き」という気持ちが表現された、世界に一つだけのアートです。自分の思いを形にする喜びを知ることは、自己肯定感の育成にもつながります。
そして、一つのものを最後まで作り上げる集中力や達成感を経験させることも大きな目的です。初めは飽きてしまうこともあるかもしれませんが、保育士のサポートを受けながら作品を完成させたときの喜びは、子どもにとって大きな自信となります。これらの経験が、今後の様々な活動への意欲の土台となっていくのです。
子ども簡単な手作り敬老の日プレゼント

子どもが作る敬老の日のプレゼントは、完成度の高さよりも、心を込めて作ったという過程が何よりも喜ばれます。特に0歳から3歳の子どもたちが作る場合は、「子ども簡単」をキーワードに、安全で楽しめるものを選ぶことが大切です。
最も定番で喜ばれる手作りプレゼントの一つが、手形や足形を使ったアートです。画用紙に絵の具で手形や足形を押し、それに少しイラストを書き加えるだけで、ゾウや花束、蝶々などに見立てることができます。今だけの小さな手足のサイズは、成長の記録としてもかけがえのない記念品となり、おじいちゃんやおばあちゃんにとって宝物になるでしょう。
また、シール貼りもおすすめです。台紙に丸や星、動物などのシールを自由に貼ってもらうだけで、カラフルで可愛らしい作品が出来上がります。指先を使う練習にもなりますし、様々な色や形に触れることで感性も刺激されます。
なぐり描きも立派なアート作品です。子どもがクレヨンで自由に描いた絵を、うちわやしおり、小物入れの飾りの一部として活用する方法もあります。子どもの純粋な表現がそのまま活かされた贈り物は、見る人の心を温かくしてくれるでしょう。これらのプレゼントは、子どもが主体的に関われる部分が多く、楽しみながら感謝の気持ちを育むのに最適なアイデアと言えます。
年齢別!敬老の日プレゼント保育園0.1.2.3歳児製作案
- 0歳児におすすめプレゼントと製作
- 1歳児に人気のハガキの製作
- 2歳児・3歳児の手作りアイデア
ここでは、子どもたちの発達段階に合わせた製作のポイントを、年齢別に表でまとめました。プレゼント選びの参考にしてください。
| 年齢 | 発達の目安 | 製作のポイント | 保護者のサポートと注意点 |
| 0歳児 | ・手足を動かす・物を握る・寝返り、おすわり | 手形・足形アートが中心。フィンガーペイントやスタンプなど、感触を楽しむ活動を取り入れる。 | 絵の具などを口に入れないよう、常に側で見守る。短時間で終えられるように準備を整えておくことが大切。 |
| 1歳児 | ・つかまり立ち、歩き始める・指先が少しずつ器用になる | シール貼り、なぐり描き、簡単なちぎり絵など、子どもが主体的に関われる部分を増やす。 | 子どもの「やりたい」という気持ちを尊重する。安全なクレヨンや、大きめで誤飲の心配がないシールを選ぶ。 |
| 2歳児 | ・走る、ジャンプする・言葉が増え、自己主張も | のりやハサミ(大人の補助付き)に挑戦。簡単な折り紙や、複数の素材を組み合わせた作品作りも可能になる。 | のりの量を調節したり、ハサミを持つ手を添えたりする補助が必要。子どもの集中力が続く範囲で取り組む。 |
| 3歳児 | ・会話が成り立つ・ごっこ遊びなどを楽しむ | 似顔絵を描く、簡単なメッセージを書き写すなど、表現の幅が広がる。自分のイメージを形にしようとする。 | 「何を描いているの?」などと声をかけ、子どものイメージを言葉にする手伝いをする。失敗しても受け入れ、達成感を味わえるよう励ます。 |
0歳児におすすめプレゼントと製作

0歳児の赤ちゃんが参加できる製作は限られていますが、この時期ならではの可愛らしさを活かしたプレゼントは、最高の贈り物になります。おすすめは、やはり手形や足形を使ったプレゼントです。
手形・足形アート
0歳児の製作の主役は、なんと言ってもその小さな手足です。画用紙やハガキに、安全なインクや絵の具で手形・足形を押すだけで、成長の記録になる特別な作品が完成します。例えば、足形を2つ並べて蝶々の羽に見立てたり、手形を花に見立てて花束のアートにしたりと、保育士や保護者が少し手を加えるだけで、心温まるアートに仕上がります。この時期のサイズはあっという間に大きくなるため、非常に喜ばれるプレゼントです。
フィンガーペイント
絵の具の感触を楽しみながら製作できるフィンガーペイントも、0歳児におすすめの活動です。赤ちゃん用の安全な絵の具を使い、画用紙の上で自由に指を動かして模様を描いてもらいます。その画用紙をハートや動物の形に切り抜いてメッセージカードに貼ったり、写真立てのフレームの飾りにしたりと、様々なアレンジが可能です。
製作を行う際の注意点として、赤ちゃんが絵の具などを口に入れないよう、大人が必ず側で見守ることが最も重要です。また、赤ちゃんの機嫌の良い時に、短時間で楽しめるように事前に準備を万全にしておきましょう。無理強いはせず、親子で感触を楽しみながら行うことが、良いプレゼント作りの鍵となります。
1歳児に人気のハガキの製作

1歳になると、指先の動きがより器用になり、自分で「やりたい」という意欲も芽生えてきます。そんな1歳児には、自分も参加している実感を得やすいハガキの製作が人気です。遠方のおじいちゃん、おばあちゃんにも郵送できる点も魅力と言えるでしょう。
シール貼りハガキ
この時期の子どもたちが大好きな活動の一つがシール貼りです。様々な色や形のシールを用意し、ハガキの上に自由に貼ってもらうだけで、世界に一つだけのオリジナルハガキが完成します。台紙にブドウやリンゴの輪郭を描いておき、その中に丸いシールを貼って果物に見立てるのも楽しいアイデアです。子どもが自分で台紙からシールを剥がして貼るという一連の作業は、集中力と指先の巧緻性を養います。
なぐり描きハガキ
クレヨンを握って描くことに興味を示す子も増えてきます。まだ具体的な形は描けませんが、その自由奔放な「なぐり描き」は、1歳児ならではの力強い表現です。子どもが描いたなぐり描きの画用紙から、よく描けている部分を切り取ってハガキに貼り付けるだけで、モダンアートのような素敵な作品になります。
ハガキの製作においては、子どもが扱いやすいように、少し大きめのシールや、握りやすい太めのクレヨンを用意してあげると良いでしょう。保護者は「ここに貼って」と指示するのではなく、子どもの自由な表現を見守り、たくさん褒めてあげることで、子どもの満足感や自己肯定感を高めることができます。
2歳児・3歳児の手作りアイデア

2歳、3歳になると、言葉でのコミュニケーションが豊かになり、自分のイメージを形にしようとする意欲が格段に高まります。手先の器用さも向上するため、より複雑な製作にも挑戦できるようになります。
似顔絵やメッセージ
2歳後半から3歳にかけて、多くの子どもが「顔」を描くことに興味を持ち始めます。丸い輪郭に目や口を描き加えた、その子ならではの味のある似顔絵は、おじいちゃんやおばあちゃんにとって何より嬉しいプレゼントです。また、簡単なひらがなであれば、見本を見ながら書き写せる子も出てきます。「だいすき」「ありがとう」といった短いメッセージを添えるのも素敵です。
ちぎり絵や簡単な折り紙
2歳児は、ビリビリと紙を破る感触を楽しむ「ちぎり絵」も得意です。ちぎった折り紙を、動物や乗り物の形の台紙にのりで貼り付けていくことで、温かみのある作品が仕上がります。
3歳児になると、直線的に折るだけの簡単な折り紙にも挑戦できます。チューリップや犬など、簡単なものを一緒に折ってカードに貼り付けると、立体感のあるプレゼントになります。
小物入れや写真立ての装飾
牛乳パックや紙コップ、空き箱などを再利用した小物入れや写真立ての製作もおすすめです。これらの土台に、子どもたちが絵を描いたり、ちぎった折り紙やビーズ、どんぐりなどを貼り付けたりして装飾します。実用的なプレゼントは、日常生活の中で孫の存在を感じられるため、特に喜ばれる傾向があります。
この時期の製作では、子どもの「こうしたい」というイメージを大人が汲み取り、それを実現するための手助けをすることが大切です。ハサミやのりの使い方を丁寧に教えたり、時には失敗を受け止めたりしながら、最後まで作り上げる達成感を一緒に味わうことが、子どものさらなる成長につながります。
まとめ:敬老の日プレゼントは保育園の製作で伝えよう
- 敬老の日は長年社会に貢献したお年寄りを敬愛し長寿を祝う日
- プレゼント選びでは年齢の数字よりも相手を思いやる気持ちが大切
- 保育園での敬老の日行事は日本の伝統文化に親しむ良い機会となる
- プレゼント製作には感謝の気持ちや思いやりの心を育むねらいがある
- 手形や足形アートは0歳児ならではの成長記録として喜ばれる
- 1歳児はシール貼りやなぐり描きなど自分で参加できる製作が人気
- 2歳児や3歳児は似顔絵や簡単な工作など表現の幅が広がる
- ハガキは遠方の祖父母にも気持ちを届けやすい定番プレゼント
- 子どもが安全に楽しめるよう製作中は大人が側で見守ることが不可欠
- 絵の具やクレヨンは子どもが口に入れても安全な素材を選ぶ
- 製作は子どもの「やりたい」という意欲を尊重し無理強いしない
- 年齢に合った道具を用意することで子どもの製作意欲を引き出す
- 失敗しても大丈夫という安心感が子どもの挑戦する心を育てる
- 完成した作品をたくさん褒めることが子どもの自己肯定感につながる
- プレゼントは感謝の気持ちを育むための素晴らしい教材となる
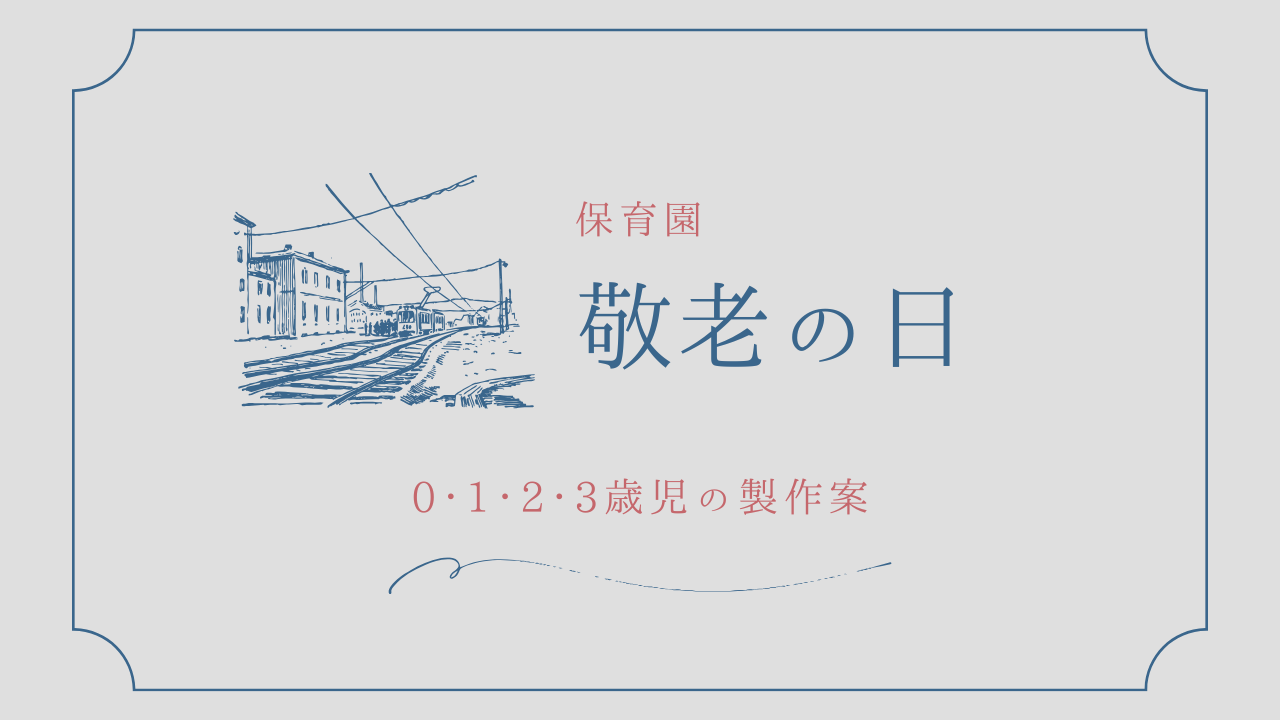


コメント